いまの力士は突き落とさず
寄り添って見守る指導法に
親が子に干渉する度合いも、かつてより高まっているようです。相撲界はどうなのでしょうか?九重龍二さんは「力士にもその傾向はありますよ」と苦笑しながら、内情を話してくれました。
「いまの子は、言葉ではなく目で訴えますよね(笑)。だから、自分から一人一人に声をかけるようにしています。俺らの修行時代は、名前で呼ばれることすらありませんでしたよ。厳しい環境の中で、勝手に育っていく。
ことわざに『獅子は我が子を千尋(せんじん)の谷に落とす』ってありますよね。まさにそれですよ。厳しくして、そこから這い上がってこいと。
でも、いまの力士は、突き落としたら這い上がってきません(笑)。だから、寄り添うしかない。付きっきりの指導が必要だと判断せざるを得ない状況です。
先代から教わったように、厳しくしたうえで突き放したっていいのかもしれません。俺はそうやって育ったから、お前らにもそうするって。これまでは、それが伝統で、そういうやり方には確たる実績があるわけですから、そうするのが手っ取り早い。
稽古場の雰囲気を作るのは
監督とか親方ではなく力士
でもいまは、メンタルの弱い子も多いですから。そういう子たちを預かる中で『以前はこうだった』というのは通じません。自分が変わらないといけないわけです。彼らの目線よりずっと下がって話を聞いてあげないと、関係が成り立ちません。
俺が電波を発して、彼らに受信させるのではなく、向こうから発した電波を、俺が受信しないといけない。まったくの逆転現象なんです。
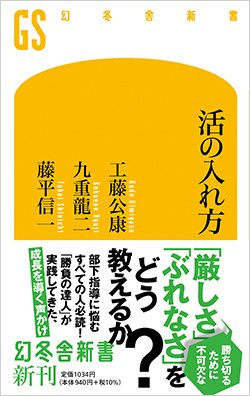 『活の入れ方』(幻冬舎新書)
『活の入れ方』(幻冬舎新書)工藤公康 著、九重龍二 著、藤平信一 著
だから、うちの力士には言ってますよ。『稽古場の雰囲気はお前たちがつくりなさい。監督とか親方が稽古場の空気をつくるんじゃないんだ』って。
これまでは、先代が張り詰めた空気をつくっていたんです。親方が敷居の上にドーンと座り、腕組みをして稽古を見ている。それだけで稽古場が緊張した空気になるんです。
でも、俺はそれをやりませんよ。『お前たちが空気をつくりなさい。笑顔があったっていいじゃないか。真剣に楽しくやって、みんなのやる気が上がるなら、それが一番だ』と。だから、いまはもう笑って稽古をします。もちろん、稽古自体は真剣そのものです」







