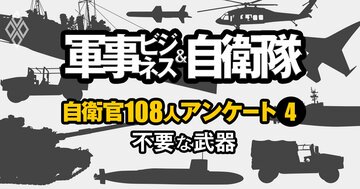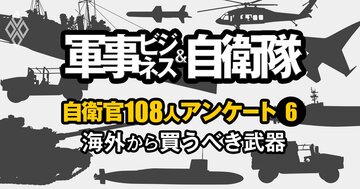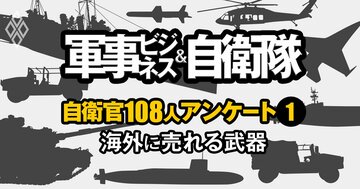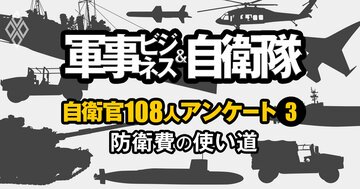23年1月には、「サイバー安全保障体制整備準備室」を創設し、「能動的サイバー防御」を可能にする法整備を進めること、が決まりました。
能動的サイバー防御は、「積極的サイバー防衛」「アクティブ・サイバー・ディフェンス」とも呼ばれます。サイバー空間を常時監視し、怪しいアクセスがあれば、攻撃元を探知して、被害が起きる前にこちらからサイバー防御を仕掛ける、という対処法です。
これは、専守防衛を定めた憲法9条、通信の秘密の確保を謳った同21条、不正アクセス禁止法、などに触れる可能性があります。そのため、新たな法整備が必要になりつつあるのです。
新しい戦場に対処すべく
「空自」は航空宇宙自衛隊へ
宇宙空間についても、主要各国はすべて、ここを戦場の1つだと考えています。
人工衛星の数を見ると、ソ連が1957年に打ち上げた「スプートニク1号」を皮切りに、世界では22年前半までの間に、約1万3000基が打ち上げられています。
近年、その規模は拡大し、22年には世界で、過去最多の2,368基の人工衛星が発射されました。中には、軍事・安全保障を目的としたもの、も含まれています。防衛省によると、20年において軍事衛星を100基以上保有する国は、米中ロの3カ国。米国は128基、中国は109基、ロシアは106基、運用していると言います。日本の稼動数は、同時点で10基前後、とされています。
種類としては、味方と敵の正確な位置を調べる「測位衛星」。遠くにいる味方部隊との通信に使われる「通信衛星」。敵の弾道ミサイルが発射されたことを、早い段階で探知する「早期警戒衛星」。敵の基地や個人などを撮影する「偵察衛星」、等があります。
どれも性能が、時代とともに向上し、最新の偵察衛星のカメラでは、解像度が少なくとも1ピクセル(画素)あたり10cm程度、だという報道もされています。これは、写っている車両の車種や、そこに取り付けられた装備。さらには、身長や体格などを把握し、個人がある程度、識別できるようになる水準、だと言います。