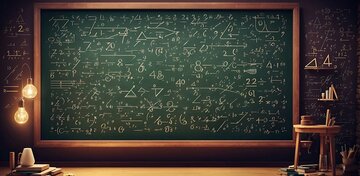写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
数学や理科の勉強で「解き方を覚える」という方法は多くの人が採用している。しかし問題の数だけ解き方を覚えるのは難しいし、公式を頭に叩き込むだけでは応用問題に対応できない。ではどのような解き方が有効なのだろうか。本稿は、篠ヶ谷圭太『使える!予習と復習の勉強法――自主学習の心理学』(筑摩書房)の一部を抜粋・編集したものです。
「解き方を覚える」よりも
「解く時のポイント」を掴む
数学や理科の勉強で採用されがちな「解き方を覚える」という方法は、あまりよいものではないです。そもそも問題の数だけ解き方を覚えるなんて無理なことです。いくつかの問題の解き方を覚えていても、その方法では応用問題に答えることができないでしょう。
それでは数学や理科のような問題を解くタイプの勉強ではどういった方法で復習するのがよいでしょうか。そこで肝となるのが「考え方のコツ」や「解く時のポイント」をつかむことです。それを実感してもらうために、有名な実験を紹介しましょう。以下では、よく知られている2つの問題を例にして説明していきます。
ある国の中心にある要塞を攻めたいが、要塞につながる道にはすべて地雷が仕掛けられており、大軍が通ると爆発する仕組みになっている。地雷を爆発させずに要塞を攻め落とすにはどうしたらよいか。
みなさんだったらこの問題をどうやって解決するでしょうか。ちなみに空軍を使ったり、地下を掘るのは反則です。あくまでも地上の道を使って攻めなければなりません。
この「要塞問題」の答えは「小さい軍隊を四方八方から送り込んで要塞部分で集結させる」というものです。確かに、小さい軍隊であれば地雷は作動しませんし、しかも、同時に四方八方から攻め込めば敵の軍隊も分散されるので返り討ちにあうこともありません。
この要塞問題とその解決方法を読んでもらった上で、以下のような問題に取り組んでもらいました(こちらは放射線問題と呼ばれています)。
がん細胞を破壊するには強い放射線を当てる必要がある。しかし、強い放射線を当てると途中にある健康な細胞まで破壊されてしまう。健康な組織を破壊せずにがん細胞を破壊するにはどうしたらよいか。
この問題はどうすれば解決するでしょうか。抗がん剤を投与するなど、放射線以外の治療法を使うのは反則で、必ず放射線を使わなければなりません。
この放射線問題の答えは「弱い放射線を四方八方から当ててがん細胞のところで集結するようにする」というものです。こうすれば、途中にある健康な細胞を傷つけることなく、がん細胞にピンポイントで強い放射線を当てて腫瘍を破壊することができるというわけです。