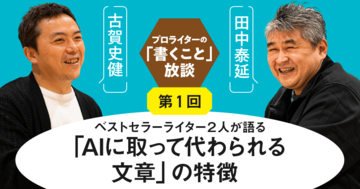写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
老齢にさしかかり、人生を振り返るため自分史を書き残そうと思い立つ。しかし、いったい何から書き始めればいいのかわからないし、自分を主人公として書くのはなんだか気恥ずかしい――。そんな悩めるシニアに向けて、英文学者、エッセイストでベストセラー「思考の整理学」の著者としても知られる外山滋比古氏が「書き出し」と「間接法」の表現について解説する。※本稿は、外山滋比古『人生の整理学 読まれる自分史を書く』(イースト・プレス)の一部を抜粋・編集したものです。
書き出しに苦労している
旧友へのアドバイスとは
郷里の親しい旧友から会いたいと言ってきた。なにごとかと思ったら、文章を書いている、いや書こうとしているが、どうもうまくいかない。書いたところを奥さんに読ませたら、「本ばかり読んでいるくせに、どうしてこんな下手な文章しか書けないの」とやられて、ショックをうけ、書く意欲もなくなった。そうは言っても、どうしても書かなくてはいけないことがある。どうしたらいいか、一度、相談にのってくれないか、というのであった。
この友人は、織田信長が今川義元を討ちとった桶狭間の古戦場の地に住んでいる。そういう由緒のある土地だから、村から史誌を書くように頼まれて、歴史好きな本人は一も二もなく承知したのである。
いろいろ故事や口伝、資料をあつめて、書くばかりになったのは半年も前だが、どうしても書き出しがうまくいかない。何度書き直したかしれないが、どうも先へ進めないで、うしろへ引きもどされるような気持になってはペンを投げ出す。それを繰り返してきたというのである。
それをきいて、それは良心的すぎるからである。だれだって書き出しには苦労するもので、書き損じが山になるという小説家のはなしもある。悲観することなどすこしもない。ただ、ひとつ心がけたいのは、うまく書いてやろうと思わないこと。かまえると、頭が固くなって、うまく働かなくなる。できるだけ、ふつうの文章を書くようにした方がいい、というようなことを言って応援した。
イギリスの大歴史家も
ローマの詩人も同じことを言う
それから、きみは、はじめのところで、つっかえて苦しんでいる。これから何度も試みれば、すらすらと書けるようになるかもしれないが、これまでの苦労を考えると、あまり楽観はできない。どうだろう、ここで方法を変えてみては。つまり、はじめの部分から書き出すのをよすのである。