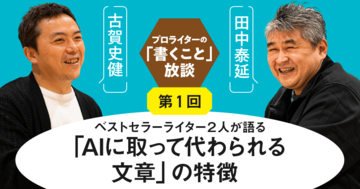どうするのか、というと、全体のうちでいま、いちばん書きやすい、おもしろそうだという部分が、あとの方にあるとしたら、それを思い切って、最初に書いてみるのである。順序のことは、全体を書いてしまったあとで、ゆっくり考えればよい。まず、とっかかりやすいところからかかる。次にもやはり書きやすい部分を見つけ、順序にこだわらずに書くのである。
この方法を教えてくれているのは、イギリスの大歴史家E・H・カーである。彼は本を書きおろすとき、第1章から順次、書いていくようなことはしないで、いちばん書きやすい、自信のある部分から書き始める。
そうすると、難しいところも勢いがついているから、わりあいにうまく乗り越えられる、という体験を披露している。
さらに、ローマの詩人、学者ホラティウスという人が「話は中ほどから(はじめるがよい)」とのべていることもつけ加えた。話の発端から順を追っていくのではなく、まん中の山場の部分を思い切って、冒頭へもってくると、よい作品になるという作法をホラティウスは書きのこしている。
そういえば、映画でも、話がはじめから始まらずに、あとの方のことを最初に投げ出して観客の興味をひいておいて、そのあと、フラッシュ・バックで、もとへさかのぼってストーリーをつづけていく手法がしばしば用いられる。
流れのある内容の文章を書くときでも、あとの方のことを冒頭へもってきて、あとで後戻りをするフラッシュ・バックの手を使ってみるのもわるくない。
一人称が控えめな日本語では
自分のことを書くのは難しい?
自分のことをじかに書くのは、なんとなく気がひける。そういう気持は多くの人にあるのではあるまいか。もともと、第一人称単数の“わたくし”ということばをおもてにあらわさずにものを言ってきた日本語では、ことにそうかもしれない。
英語などだと、“わたくし”(I)を使わないでは何も言えないが、日本人は、“わたくし”を出さずに、いくらでも文章を書くことができる。