小さい頃からの「ネット漬け」が
発達に影響することもある
こうした現場の“肌感覚”を裏付ける研究もあります。千葉大学と国立成育医療研究センターの研究グループは2023年、乳幼児期の子どものメディア視聴時間と発達の関連を明らかにしました。
この研究によって、1歳でもメディア視聴時間が長くなるとコミュニケーションの発達領域に影響を及ぼすことが明らかになりました。
2023年1月、静岡県で中学生の娘が母親を刺殺する事件が起きました。「スマホの使い方を巡って母親とトラブルになった」という供述が世間を震撼させました。この事件が「対岸の火事ではない」と感じた中学生の親も少なくありませんでした。
「このままでは日本が滅びてしまいそうで心配です」
取材で出会った塾講師の女性は、ネットの世界に溺れる小中学生へのやりきれない思いを吐露しました。女性はゲーム沼から抜け出せず、学校や塾にも通えなくなった小中学生とその家族の苦しみに寄り添ってきました。
女性が対応に当たった深刻なケースでは、祖母や母親に暴力を振るう子、ゲーム中に失神して記憶が飛ぶ子、幻聴や幻覚がある子もいて入院を余儀なくされたケースもありました。
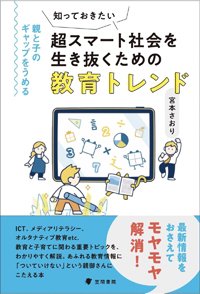 『知っておきたい超スマート社会を生き抜くための教育トレンド:親と子のギャップをうめる』(宮本さおり、笠間書院)
『知っておきたい超スマート社会を生き抜くための教育トレンド:親と子のギャップをうめる』(宮本さおり、笠間書院)
2019年5月、世界保健機関(WHO)は「ゲーム障害(Gaming disorder)」を国際疾病分類の一つに認定しました。国際疾病分類とは、医療機関での診断や治療を必要とする疾病の世界的な統一基準のこと。ゲーム障害は世界規模の病となりました。
生活や心身の健康に支障をきたすほどゲームに没頭し、不登校や引きこもり、家庭内暴力、食事を摂らないといった深刻な問題を引き起こします。アルコールやギャンブルと並んで、治療が必要な疾病として取り扱われるようになりました。
動画やSNSなどのオンラインコンテンツを含むいわゆるネット依存については国際疾病に認定されていませんが、さまざまな問題が起きています。カナダでは人気ゲーム『フォートナイト』をプレイした子どもが依存症になったとして、親たちが集団訴訟を起こしました。世界中の親が悩まされています。







