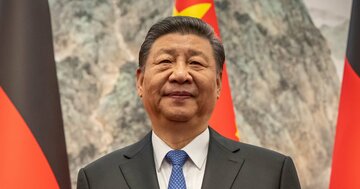写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
2010年に名目GDPで日本を抜いた中国は、世界2位の経済力に物を言わせ、空母を続々と就役させるなど軍拡の一途。その自信を背景に、外交当局が台湾や日本などの周辺諸国に繰り出すロジックもまた、攻撃的で好戦的で独善の色を強めている。こうした中国共産党の「戦狼外交」の目指すところはどこなのだろうか?我が国の政財官界には、いまだ「日中友好」論が根強いが、外務省でインテリジェンス担当の国際情報統括官を務めていた筆者の目には、違って見えるようだ。※本稿は、山上信吾『中国「戦狼外交」と闘う』(文藝春秋)の一部を抜粋・編集したものです。
コワモテぶりを内外にアピールして
出世の階段を駆けた前外相・秦剛
戦狼外交の先駆的存在とみなされてきたのが、前外相の秦剛(しんごう)だった。2022年秋の共産党大会で中央委員(編集部注/中国共産党の最高指導機関「中央委員会」のメンバー。約200人しかいない)に抜擢され、12月30日には最年少で外交部長(外務大臣)に就任した。まさに、若きスターだった。その昇進ぶりが目覚ましかっただけに、公の場から姿を消して2023年7月に解任された凋落ぶりもまた衝撃的だった。
1992年に外交部に入った秦剛の名前が知られるようになったのは、中国外交のスポークスマンを務めたからである。2005年から新聞司(報道局)の副司長、2011年以降は新聞司長(局長級ポスト)を務めた。外交部の記者会見の際に、こわもてで強硬な発言でたびたび物議を醸してきた姿を覚えている読者も多いだろう。
また、他国の首脳や外務大臣を呼び捨てにし、その発言を公の場で痛罵するなど、外交上のプロトコルを逸脱した言動が強烈で異様な印象を与えた。その意味では、忘れがたいインパクトを残した男だ。
外相就任後、最近はまず中国の要人から耳にすることがなかった「日本軍国主義の復活」などという歴史カードを振りかざした批判を一度ならず口にしたのも秦剛だった。歴史カードの政治的利用こそは、戦狼外交官のたしなみであり、イロハのイといえるかもしれない。
林芳正外相(当時)と面談した際、自分よりも年長である日本の外相を見下したようなぞんざいな態度を露骨にとり、メディアの前での写真撮影の際にあからさまな軽侮の表情を浮かべたことに観察眼の鋭い人は気づいたことだろう。
秦剛とすれば、温和でおとなしく、中国人の目に弱々しく映る日本の外相を踏み台にすることによって、中国国内に向けてアピールしたいとの思惑があったに違いない。
クローズな会食の場での秦剛は
受け身一辺倒の寡黙な男だった
その秦剛は2010年から1年強の間、駐英大使館のナンバー2ポスト(次席公使)に就いていた。2009年からほぼ3年間ロンドンの日本大使館に政務担当公使として駐在していた私は、秦剛と昼食で同席したことがある。
駐英ドイツ大使館の次席公使が主催した、ハイドパーク沿いの瀟洒なドイツ公使公邸でのランチだった。当日は欧州主要国(英仏独)と東アジア主要国(日中韓)の大使館次席クラス6人が集まった。英外務省からは当時極東担当部長であったジュリア・ロングボトム(現在の駐日大使)が出席していた。