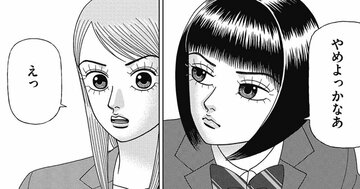写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
世界のトップ大学では、男女比がほぼ半数が当たり前。東大での女子率は2割ほど。それを3割まで増やそうと、東大当局は様々な施策を試みている。女子の大学進学率が急増した1960年頃からしばらく、女子大生亡国論が跋扈した。その頃、東大の事務官の尾崎盛光は、東大の女子学生に向けて、「『わたしは日本最高の花嫁学校にいる』という誇り」を持つよう促した。※本稿は、矢口祐人『なぜ東大は男だらけなのか』(集英社新書)の一部を抜粋・編集したものです。
女性はどうせ家庭に入るから
教育をしても無駄になる
早稲田大学文学部教授の暉峻康隆は、1962年に「女子学生世にはばかる」という論を『婦人公論』(3月号)誌上に発表し、彼が教える国文科をはじめ、文学部に女性が急増する現状を大きな社会問題として訴えた。
暉峻によれば、私大の文学部に来る女性は、結婚のための教養を身につけるためだけに来ている。そういう学生が増えると「学者ならびに社会人の養成を目的とする大学の機能にひびが入る恐れがある」。終戦直後に入学した女性は目的意識が明確で「男に負けるものかといった対抗意識」を持っていたが、近年の女性学生は「青春を謳歌しながら教養を身につけ、4年の間にあわよくば将来の相手を物色しようと」しているに過ぎない。「そういう目的にかなった女子大学が沢山あるのだから、なるべくそちらへいってもらいたい」。
彼女たちが早稲田大学文学部に来ることに暉峻は強い不満を覚えていた。
女性の増加に危機感を抱いていたのは早稲田の教員だけではなかった。慶應義塾大学文学部で国文学を担当していた池田弥三郎は暉峻のエッセイの翌月、同じく『婦人公論』誌上で「大学女禍論」を発表し、「大学における女族の進出」は「女禍」であると主張した。
「文学部における男女学生の比率は、五分五分か、今年あたりは悪くすると、はかりが女子の方に傾いて、四分六ぐらいになるかも知れない」と池田は危惧していた。