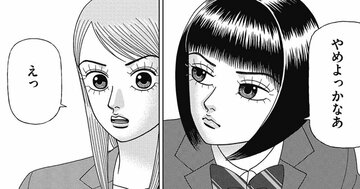女性学生の親は寄付金を多く出さないから経営の足しにならないうえ、「男は狭く深く進む」が「女は一般的に広く浅い」ので「大学がその学問の将来を托する上において、女は原則的に悲観的期待しかよせられない」。おまけに、「4年間めんどうをみて世の中に送り出し」ても女性の「大多数が『結婚』をもって、一応その人生の終点」となってしまうから、ずっと社会に出て働く男と比べて、教育が無駄になってしまう。だから大学に女性が増えることは「禍」であると池田は主張していた。
さほど女子が増えていなかった
東大でも「女禍」論が飛び出す
早稲田や慶應とは対照的に、東大の女性学生数はこの当時もさして増えていなかった。入学者は毎年60名程度で、19名だった1946年と比べれば3倍ほどになっていたが、それでも全体の5%にも満たなかった。暉峻や池田が憂えていた私大文学部の状況は東大のキャンパスには見られなかった。
それでもこのような論に同調する声が教員のあいだに見られた。たとえば教養学部でフランス語を担当していた田辺貞之助は、暉峻の女性学生批判に強く同意していた。
田辺は暉峻の論が出た同じ月に、暉峻と慶應義塾大学文学部教授の奥野信太郎とともに、TBSラジオ「ただいま放談中」という番組に出演し、「大学は花嫁学校か」を論じていた。その様子が『早稲田公論』の創刊号(1962年6月)に活字化されている。