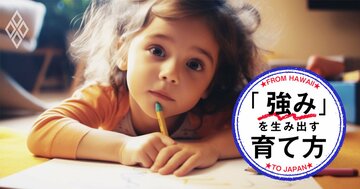写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
子どもの学習タイプは大きくわけると、習得寄りの「こつこつ」型と思考寄りの「ひらめき」型がある。どちらにも良さがあり、その子に合った勉強の進め方がある。そして最大のポイントは、各タイプ別の「やってはいけない指導法」を把握しておくことなのだーー。本稿は、佐藤 智『10万人以上を指導した中学受験塾 SAPIXだから知っている算数のできる子が家でやっていること』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の一部を抜粋・編集したものです。
習得寄りの「こつこつ」型
思考寄りの「ひらめき」型
算数には「思考」と「習得」の両方が必要ですが、この両方が得意な子はほぼいません。SAPIXでも子どもが「思考」と「習得」のどちらかが不得意で、相談に来られる保護者は多くいます。
たとえば、「パッと問題が解けるタイプではないので、中学受験に向かないでしょうか?」「何度注意しても算数の式を全然書かないけれど、うちの子は大丈夫でしょうか?」といった相談はよくあります。誰にでも得意・不得意はあるので、それぞれの子どもの傾向に合った学習方法を見つけることが大切です。
子どもの学習タイプは大きくわけると、習得寄りの「こつこつ」型と思考寄りの「ひらめき」型があります。
これは「どちらかというと、こちらのタイプ」とゆるやかにわけられるもので、はっきり区別するものではありません。これらのタイプによって、算数を学ぶときの注意点や保護者の接し方が異なってくるので、それぞれの特徴をご紹介します。
「間違えたくない」
“こつこつ型”の特徴
こつこつ型は、言われたことを真面目にこなそうとするタイプです。
一方で、新しいことを自分なりに考えることに対しては苦手意識を持っているケースが多いでしょう。
このタイプは「間違えたくない」という思いが強い特徴があります。失敗が怖いから、初見の問題には手をだしにくい。そうすると、自然と考える練習が不足して、どんどん思考することに苦手意識を持っていきます。
わかっていることはしっかり書きますが、見たことのない問題は「わからない」と言って手をつけないことがある子は、このタイプです。
こつこつ型の子には、まずは「間違えてもいいんだよ」「間違えることが勉強だよ」と伝えてください。間違いへの恐怖心をなくすことからスタートしましょう。
じつは、算数はメンタル面が大きく影響する教科ですから、失敗を恐れる心を取りのぞくことは最重要ポイントなのです。
あとは、「うちの子、本当に初見の問題が弱いわねぇ」といったレッテルを決して貼らないこと。そういった発言を保護者が続けてしまうと、本当に自分なりに考えることが苦手になってしまいます。