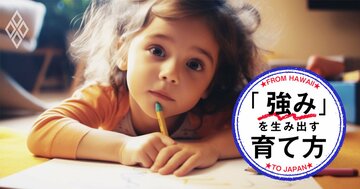その場合には、その子自身が「困った!」と思ったタイミングで、「この練習が必要なんじゃない?」と手を差しのべることがポイントです。上の立場から指示するように伝えるのではなく、相談にのってあげる話し方を心がけるとうまくいくでしょう。
ひらめき型の子に対しては、保護者が「ちゃんと勉強しているの?」「パパッと片づけないで、きちんとやりなさい」といった声がけをしがちです。そうすると、本人はストレスを感じて勉強が嫌いになってしまうこともあるので気をつけましょう。
ひらめき型のまとめ
【特徴】
・挑戦が好きで、自分なりの答えを見つけたい
・反復練習や繰り返し作業が苦手
【やってみてほしいこと】
・小さいときから、反復練習が必要な勉強は習慣化しておく
・小学校中学年以降は、反復練習が必要だと子ども自身が実感するタイミングで、習得の練習をすすめる
【特徴】
・挑戦が好きで、自分なりの答えを見つけたい
・反復練習や繰り返し作業が苦手
【やってみてほしいこと】
・小さいときから、反復練習が必要な勉強は習慣化しておく
・小学校中学年以降は、反復練習が必要だと子ども自身が実感するタイミングで、習得の練習をすすめる
こつこつ型もひらめき型も
タイプの違いで優劣はない
「うちの子は、こつこつ型(ひらめき型)かも?」となんとなくイメージがついたでしょうか。
タイプの違いがあることを踏まえておけば、ひらめき型の保護者も、こつこつ型と比較して心配になることが減るはずです。
また、こつこつ型の子はひらめき型の子に憧れて、「自分にはこんなことはできない」と自己評価を低くしてしまうことがよくあります。「あんな発想はできない」「私は地頭が悪い」と思ってしまう傾向があるのです。
でも、劣等感を抱く必要はまったくありません。
中学入試の算数では何ステップも踏まなければ解けない問題が多く出題されます。そういう問題に対して、粘り強くミスなく処理をしていくことが、こつこつ型の子は得意です。こつこつ型とひらめき型は単なるタイプの違いであって、優劣は一切ありません。
4年生ぐらいまでは、比較的単純な問題が多いので、ひらめき型の子は直感でパッと解けることが少なくありません。先ほどお伝えした通り、この姿を見て、こつこつ型の子は自己評価を下げてしまうことがあります。