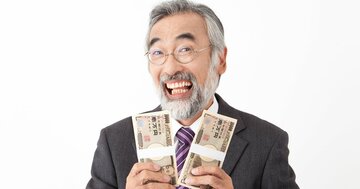あなたのビジネス経験は、地域経済を動かす「カタリスト(触媒)」として、あるいは産官学をつなぐ「プロデューサー」として、渇望されている(写真はイメージです) Photo:PIXTA
あなたのビジネス経験は、地域経済を動かす「カタリスト(触媒)」として、あるいは産官学をつなぐ「プロデューサー」として、渇望されている(写真はイメージです) Photo:PIXTA
今放送中のNHK朝ドラ『ばけばけ』の主人公・小泉八雲は、異文化で得た知を次の社会に生かした先駆者でした。明治の招聘外国人たちは、現代でいう「サードキャリア」を実践し、日本の未来を変えた実務家教員です。あなたも、これまでの経験を教室で語り、学生の目が輝く瞬間を迎えるかもしれません。前回に続き、平尾清さんの著書『ビジネス経験を活かしきる「40代から大学教授」という最高の働き方』(青春出版社)から、あなたの実務経験が求められる大学教授という可能性についてご紹介します。
日本は今、「第二の維新」を迎えている
突然ですが、あなたは今の日本が、歴史的な大転換点にあることにお気づきでしょうか? 私は、現代が「明治維新」以来の、社会構造が根底から変わる時代に突入したと確信しています。
人口減少、超高齢化、そしてAIの台頭。これまで当たり前だった社会のOSが、音を立てて書き換わろうとしているのです。
明治維新の時代、日本を近代国家へと導いたのは誰だったでしょうか?
それは、書物のなかだけで学んだ国内の学者だけではありませんでした。日本が未来を賭して有名大学に招聘したのは、現場を知る、異分野の“実践者”たちだったのです。
たとえば、東京大学で教鞭を執り、大森貝塚を発見したエドワード・S・モース。彼は動物学者でしたが、その実践的な探究心は、日本の考古学という新たな扉を開きました。
NHK朝ドラ『ばけばけ』のモデルであり、『怪談』で知られるラフカディオ・ハーン(小泉八雲)も、もとは新聞記者です。彼の新鮮な視点は、東京帝国大学の学生たちに英文学の面白さを教え、日本人が自国の文化の価値を再発見するきっかけを与えました。