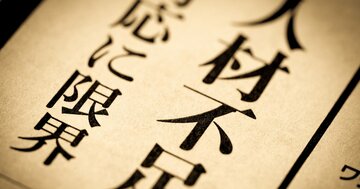日本の医療サービスは
世界でも稀有なほどの高水準
診療報酬や介護報酬の低下は消費者が直面する価格の低下にもつながるため、超過需要が常態化し、サービスの順番待ちが頻発することになる。
要介護度が低い利用者などに対する優先度が低いサービスについては、それを受けることができないような事態も発生するだろう。
一方で、そもそも、医療・介護サービスについて安くて質の高いサービスにフリーアクセスできる環境を実現するということは、非常に難しいことである。
高度な医療環境が整っていても医療費が高額で一般市民には手が届かないような米国の市場や、無料の医療が誰でも受けられるが軽度の疾患については診療の予約すら取れない英国の市場のように、諸外国を見渡せば、医療・介護サービスを受けるにあたって何かしらの制約がある国は多い。
こうした観点でみれば、日本ほど安くて質の高い医療・介護サービスを思う存分に受けられる環境を整備している国は、ほかに見当たらない。
こうした日本の手厚い医療・介護サービスの体制は、その反面として税・保険料の上昇を通じ、現役世代を含めた国民負担の増加につながっている。
また、医療・介護保険制度による低い自己負担率も、消費者側からみれば大量の医療・介護サービスを消費することを可能にしている一方で、本来提供されうる以上の医療・介護需要を誘発している側面もある。
今後を展望すると、高齢化のさらなる進展に伴って医療・介護産業で生じた余剰を求め、他産業に従事していた労働者がこれまで以上に医療・介護産業に流れ込むことになるだろう。
そうなれば、日本社会ではただでさえ少なくなっていく働き盛りの希少な人材が、医療・介護産業にますます吸収されてしまうことになる。
トレード・オフか技術革新か?
医療・介護サービス継続のための方策
このような課題を踏まえれば、これから先の超高齢化時代における医療・介護サービスのあり方については、日本社会全体として何を優先するのか考えなければならない局面に差し掛かっているのではないだろうか。