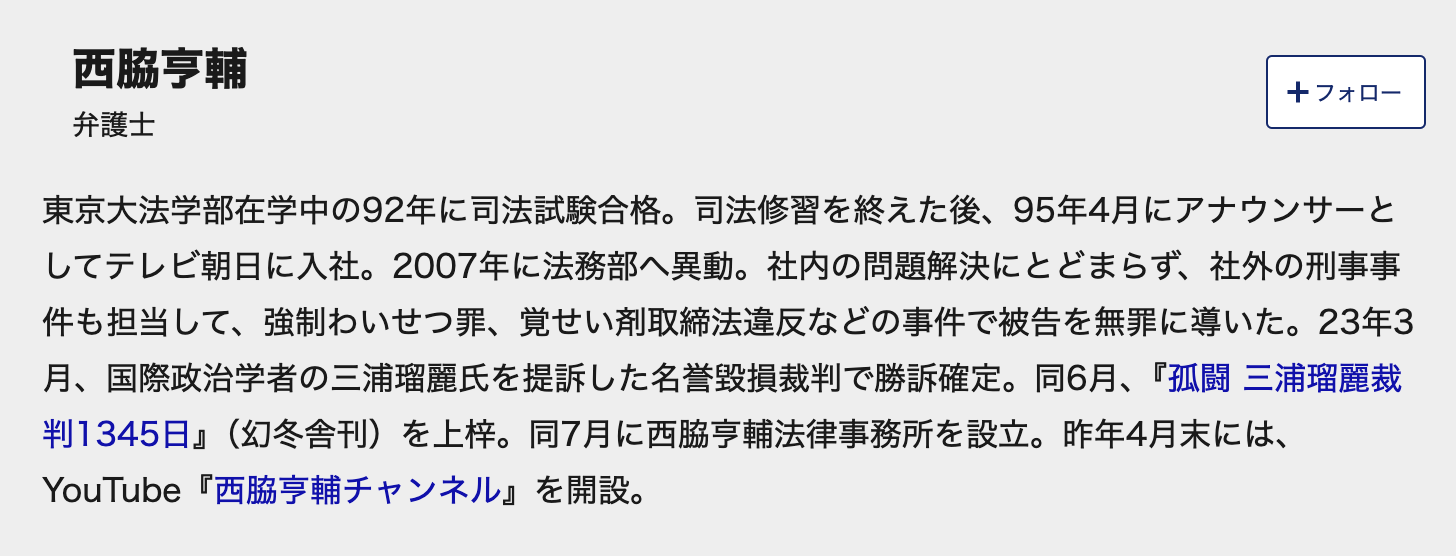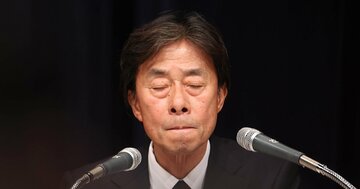テレビ局は、全国に放送網を持つうえに影響力も大きいので、多くの方が大きな組織をイメージするかもしれません。しかし、実は知名度ほど組織は大きくなく、キー局でも社員数は大体1000人〜1300人程度。しかも、その多くは現場に赴く記者や番組を制作するディレクターで、「会社や部署を挙げて巨大なプロジェクトを推進する」というよりは、それぞれが割り振られた取材や制作をしています。
従業員は「ネタを取ってくる」とか「視聴率を取る」ことに関心はあっても、自社の企業統治に対する関心は薄くなりがちです。そうなると、経営陣が組織のガバナンスよりも自分たちの判断を優先していても、従業員はあまり気にせず自分の仕事に専念する。さらに労働組合が経営に対してあまり強くない会社も多く、経営者から緊張感が失われガバナンスが緩くなるケースもあります。
日本テレビ:1353人(2024年4月1日現在)、テレビ朝日:1239名(2024年1月現在)、TBS:1072人(2024年3月31日現在)、テレビ東京:790名(2024年3月31日現在)、フジテレビ:1169名(2024年3月31日現在)
フジテレビの場合はさらに特殊な事情があります。取締役を40年以上務め、同社内で絶大な権力を持つとされる日枝久さんの存在です。フジメディアホールディングスとフジテレビの取締役相談役やフジサンケイグループの代表など様々な肩書を持ってグループ内に君臨しています。強い経営者がいる会社というのは、当人とその周りの側近たちであらゆることを決めようとする傾向があります。
経営における重要事項は、そのサークルの中だけで決まってしまう。サークルに入れていない社外取締役や取締役、部署は決まったことを伝えられるだけ、もしくは会議があっても形式だけというように組織の意思決定が骨抜きにされるのです。
中居さんをめぐるトラブルのような会社の一大事が発生したときすら、権力者を中心とした少人数ですべてを処理しようとしました。 コンプライアンス推進室には情報すら共有しない。それは、ツーカーの仲のサークルの中に部外者が入ることで、異論が上がってきたり、自分達で結論をコントロールすることができなくなったりするから。つまり、不確定要素が増えることを嫌うのです。
よく言えば家族的、悪く言えば前時代的――。そうした経営が一部のテレビ局には残っていて、その1つがフジテレビだったんだろうなと考えられます。フジテレビのガバナンス不全が発生した経緯は、第三者委員会の報告で明らかにされると思いますが、今回はそもそもテレビ局がガバナンス不全に陥りやすい理由について解説しました。