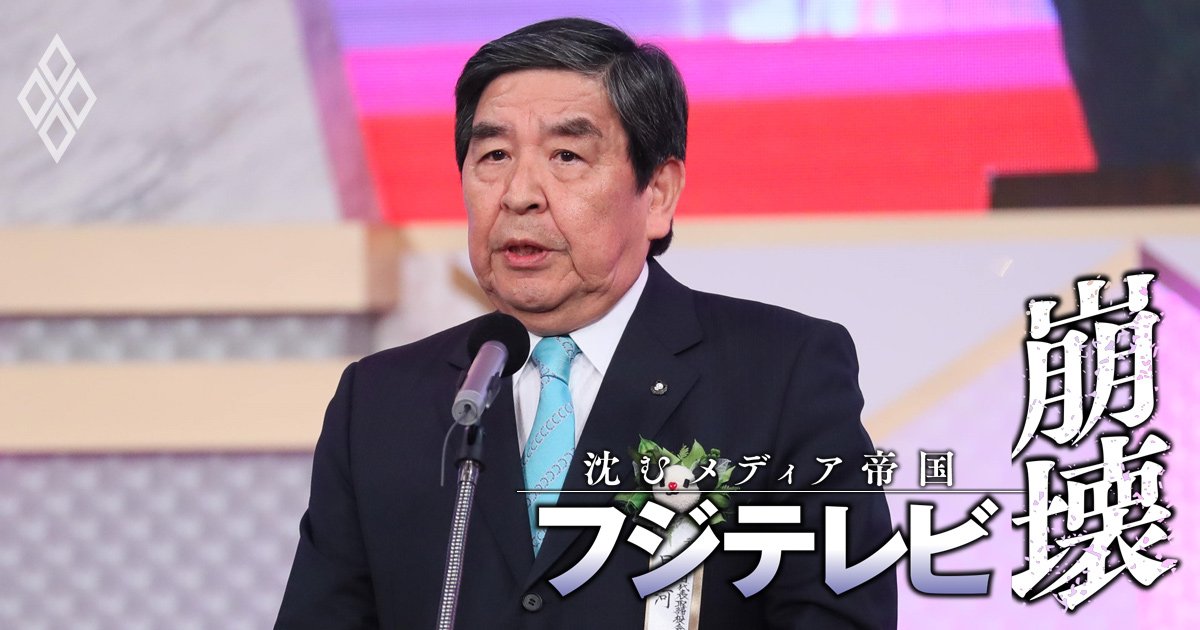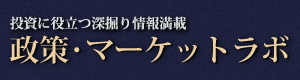それは、短期間で整備を進めれば、設備更新の必要性も短期間に集中して発生してしまうことだ。
仮に、社会資本の整備が長い年月をかけて行われたのだとすれば、耐用年数が来る時点も徐々に到来するだろう。だから、長い時間をかけてそれに対応することができる。
しかし、日本の場合には、施設が老朽化して修繕や再投資が必要になる事態が集中的に起きることになる。
ところが、経済全体の成長率は、施設を整備していた時代とは全く変わり、落ち込んでしまった。したがって、十分な更新を行うだけの経済的な資源がない。だから完全には維持できないということになる。
いわば、過去に成功したことの重みを、いま(あるいは、これから)負っているのだ。
高度成長期に社会資本の整備を進めていたとき、「将来成長率が低下すれば、これらの施設を維持できなくなるだろう」などとは、誰も考えなかった。増加する需要に対応することだけが考えられていたのだ。
欧米の都市は、長い年月をかけて徐々に形成された。したがって、社会資本の更新投資がある期間に集中するという問題も起こらなかった。この問題は、多分に日本の「特殊問題」なのである。日本は世界のどの国も経験することのなかった難しい問題にこれから直面することになる。
危機感が薄い「令和版列島改造計画」
改造より現在の生活環境維持必要
石破茂首相は、今国会での施政方針演説の中で、地方創生を柱に「令和版列島改造計画」を行うと表明した。そして、これまでは、強い日本、豊かな日本を目指していたが、これからは楽しい日本を作るとした。
令和版列島改造計画の最も大きな問題は、日本が抱える社会資本の危機的な状況に対する危機感があまりに薄いことだ。
将来の日本にとって必要とされるのは、列島を改造することではなく、現在の生活環境をどのようにして維持していくかだ。
列島改造計画では、ソフトが強調されている。もちろんソフトは重要だ。しかし、社会資本の維持・補修は、ソフトだけでは解決できない。大量の物資が必要なのだ。
列島改造計画が目指すように地方に経済活動を移せば、そこで新たに社会資本が必要になる。そのためには、整備の資源確保のために経済成長が実現していなければならない。一方で従来の社会資本を更新しながら、他方で新しい社会資本の建設ができるだろうか?
そのためには、日本の経済成長率が高まり、豊かにならなければならない。
だが、人口減少が進み、どんなに頑張っても、かつての高度経済成長を再現することは不可能だ。
したがって、現在の生活圏をそのまま維持することは困難であり、それを縮小することが要求される。生活圏の縮小とは、はっきり言えば、「現在住んでいる地域を見捨てる」ということだ。これは、大変大きな利害関係の調整を伴う、極めて難しい問題だ。
こうした困難な問題に対処するのが、政治の役割だ。
(一橋大学名誉教授 野口悠紀雄)