「障害は個性のひとつ」と口にする側は「包摂のレトリック」として語っているつもりなのに、受け取る側にはどうしても「差異化のレトリック」の残像がつきまとってしまうのである。
学校の道徳科のカリキュラムでも個性は「輝くもの」と教えられている現実があるわけだから、それは無理もない話ではある。
「そんなきれいな言葉で語られることには違和感がある」などという反発が表明されるのは、おそらくこうした事情によるものであるだろう。
今や「個性」の語には、それ自体にすっかり価値的なイメージが付着してしまっているのであり、そのことが、いわばコミュニケーション上の齟齬を生じさせている一因となっていることは十分に考えられるはずである。
「障害は個性」が
口先だけの態度となる傾向
そして第3として挙げておきたいのは、そもそもそれが「レトリック」にすぎないことの限界である。つまりそれは、最終的に「口先だけ」の態度となる傾向をはらんでしまう。この話法の中にしばしば指摘されている「軽薄さ」とは、要するにそういうことなのではないだろうか。
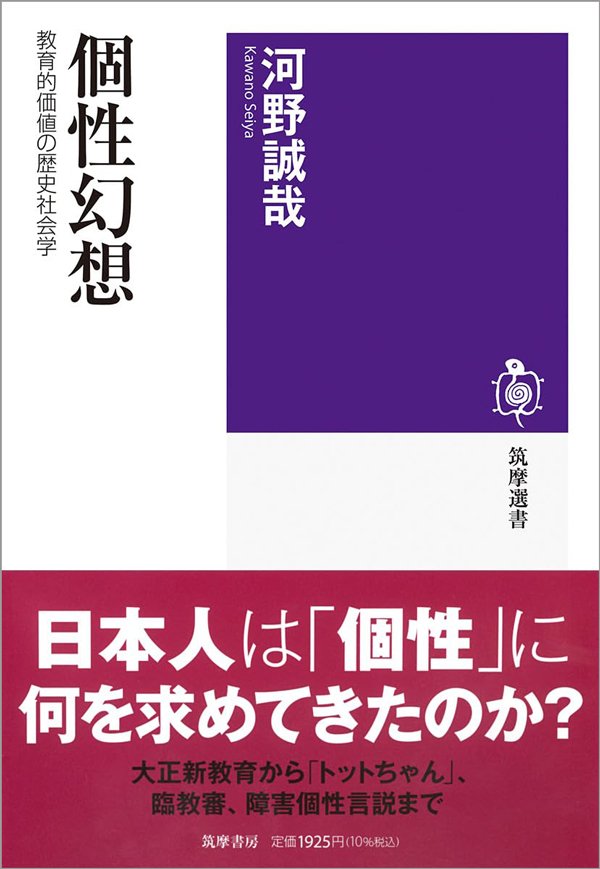 『個性幻想――教育的価値の歴史社会学』(河野誠哉、筑摩選書、筑摩書房)
『個性幻想――教育的価値の歴史社会学』(河野誠哉、筑摩選書、筑摩書房)
もちろん、「レトリック」であることが、ただちに「口先だけ」の軽さを意味するわけではないだろう。しかしながら、当初段階では崇高な理念に裏打ちされた真摯な言葉であっても、また語っている当人にすれば心からの善意のつもりであっても、それが決まり文句として繰り返されているうちに陳腐化が生じ、徐々に薄っぺらな言葉に見えてくるということはあるだろう。
したがって、このレトリックに魅力を感じ、それを口にする人間が増えるほど、かえってそれへの反発の声も高まるというパラドキシカルな状況がここには展開しつつあるようにも思われるのである。







