季節によっても、音源には変化が生じる。まず何といっても顕著なのが夏である。筆者はセミが好きで、夏場はセミの鳴き声と鉄道を絡めた音を探して各地を旅している。種類によっても、地域によっても、その声色は異なっている。よく知られているのは、西日本ではクマゼミやアブラゼミが多く、関東地方はミンミンゼミが多い。こういった季節感や地域差をサウンドスケープのなかでも感じたい。
カエル、スズムシ、コオロギ
美しい鳴き声が彩りを添える
また、6月頃ならカエルの大合唱も楽しめる。田園地帯であればなおさらで、例えば関東鉄道常総線の宗道(そうどう)駅付近や、小湊鉄道の川間駅や飯給(いたぶ)駅などは、気動車の音にカエルの合唱を組み合わせることができる。特に小湊鉄道の場合、キハ200形のDMH―17系エンジン音とカエルの鳴き声を絡められる。停車中のアイドリング音もしっかり記録したい。
晩夏から秋にかけての時期は、スズムシやコオロギといった虫たちが美しい鳴き声を奏でてくれる。これは線路端だけでなく、駅構内でも耳にできるので、夕方以降はホームでその音色を楽しみたい。筆者はこういった虫と貨物列車の絡みが好きで、九州の小倉駅での録音を思い出す。虫たちが鳴いているところに機関車の音が響き、貨物列車が通り過ぎていく。そして、ジョイント音(6*)が徐々に小さくなっていき、虫たちの声が再び存在感を示し始める。秋口ならではの音源である。
(5*)…編集部注/列車がレイルの継ぎ目を走行中に鳴る「ガタンゴトン」という音
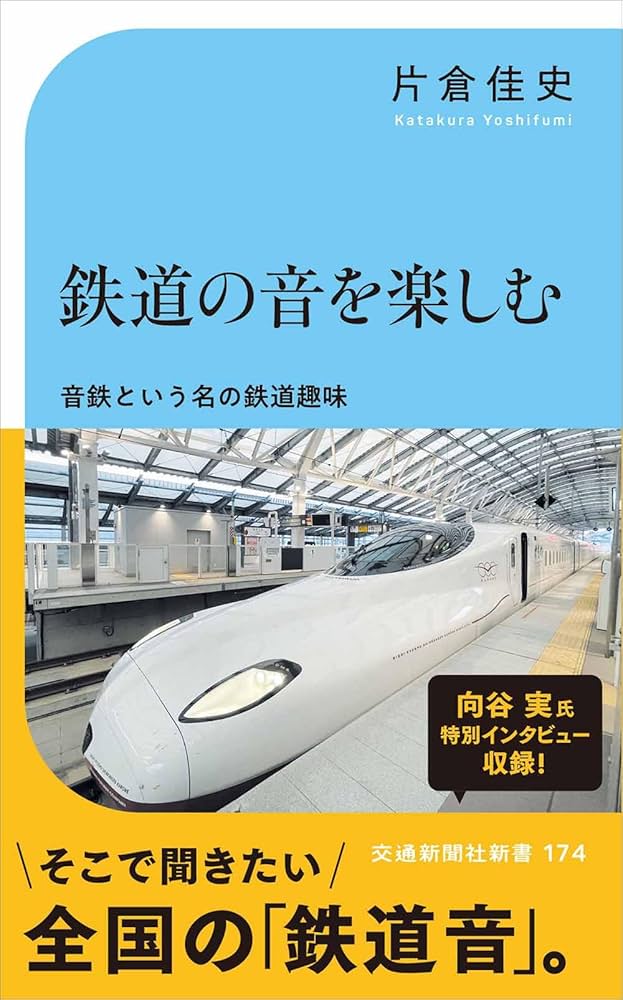 『鉄道の音を楽しむ 音鉄という名の鉄道趣味』(片倉佳史、交通新聞社)
『鉄道の音を楽しむ 音鉄という名の鉄道趣味』(片倉佳史、交通新聞社)
冬にも冬らしい音の風景がある。雪国においての録音は当然、寒さとの戦いのなかにある。雪は音を吸収するため、北海道の車両には甲高い警笛が装備されている。これだと遠くからでも警笛を聴くことが可能である。また、打鐘式の旧式踏切が残っている津軽鉄道や弘南鉄道、北陸鉄道、えちぜん鉄道などでは、雪によって静寂の世界となった土地に寂しげな警報音が鳴り響く様子を耳にできる。
なお、冬はレールの継ぎ目が開いているため、ジョイント音の録音にも向いている季節でもある。
※なお、“音鉄”趣味を楽しむにあたり、







