研究結果から生まれた
混雑時にはワルツの発想
――まさに“ストーリー”を感じますね。
最初は“一曲入魂”というか、気合を入れて作っていたのですが、制作の過程で繋がりが見えてきました。そして、三条駅については、ここは終点ではなく、「まだ終わりませんよ」という含みを持たせ、続きを感じさせるメロディにする。こういうのが楽しくなってきて、他にもやってみようと思うようになりました。たとえば、特急用の下り(大阪方面)は、大阪に向かうわけですから、アーバンな感じに仕立てています。
――普通列車用のメロディにも仕掛けはあったのでしょうか?
普通列車用については、制作の過程である発見をしました。これはささやかな研究成果だと自負しているのですが、混雑している時間帯にふさわしい旋律を考えていたところ、“三拍子”に行きついたのです。つまり、ワルツ(円舞曲)です。三拍子というのは割ることができないリズムですから、なんとなく立ち止まりにくいんです。ですから、三拍子で楽曲を作っていきました。
――最後に、向谷さんにとって、趣味と仕事の境界線についてお教えください。
自分のなかには境界線というものはないように思っています。音楽も鉄道も、自分のなかではつながっていて、音楽だけでもないし、鉄道だけでもないような気がします(笑)。ただ、経営者という側面で言うと、いろいろ勉強しなければならないですし、決断もしなければならない。私は40年近く会社を経営していますが、当然、好調なときもあれば、そうでないときもあります。ただ、音楽制作と鉄道趣味が1つになるというプロセスは、どんなときも、ごく自然なかたちで常に仕事に繋がってきたと思っています。
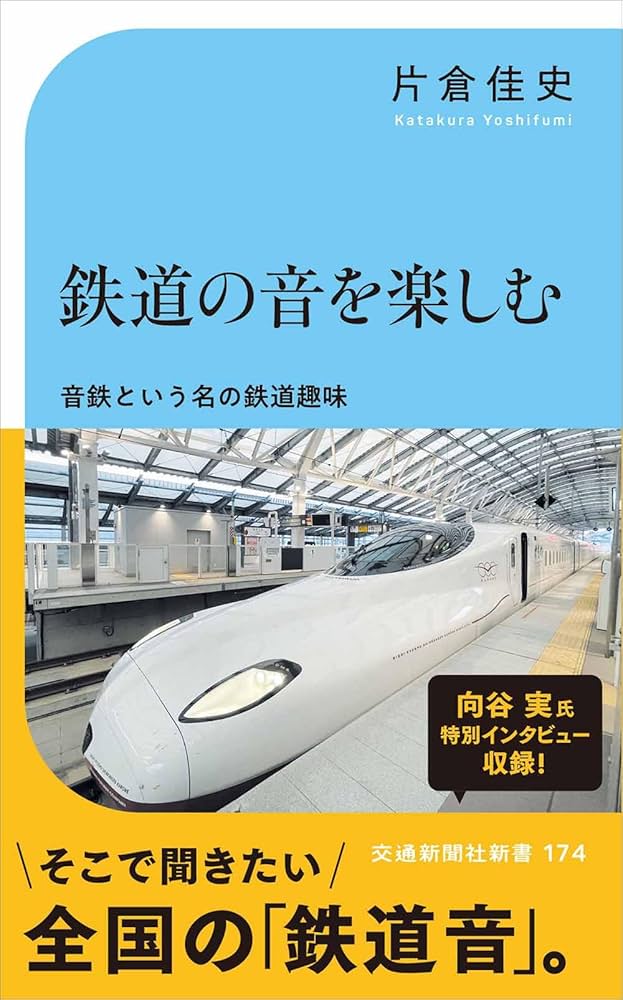 『鉄道の音を楽しむ 音鉄という名の鉄道趣味』(片倉佳史、交通新聞社)
『鉄道の音を楽しむ 音鉄という名の鉄道趣味』(片倉佳史、交通新聞社)
――音楽と鉄道が自然なかたちで、自身のなかでつながっているということですね?
これはクリエイター全体に言えることなのですが、自分に内在している様々な要素があって初めて創作活動は続けられます。私の場合も、鉄道だけではないのですが、やはり創作活動について、鉄道趣味は大きな影響を与えてきたと思います。幸い、私には趣味と仕事の境界線はありませんが、仕事や暮らしとのバランスを保ち、自身の人生を盛り上げていく。そういう生き方については、後悔はないですね。
――ありがとうございました。
※なお、“音鉄”趣味を楽しむにあたり、







