「真の戦犯」が裁かれず
現経営陣がスケープゴートに
以上の点を踏まえ、筆者の個人的見解を3点ほど付言したい。
第1に、有税、無税を問わず、必要な引当、償却を行うことを謳った新基準は、国際的にも通用し、考え方としては妥当なものである。また、透明性の高い銀行監督制度への移行も妥当と言える。むしろこうした制度への変更の遅れこそが問題であった。
第2に、新会計基準が唯一の公正な会計慣行という市民権を得ていたとはいえない。決算承認制度は1996年まで、不良債権償却証明制度は1997年7月まで実施されていて、それと並行するように97年3月に会計制度を変更したので、長銀が粉飾とされた98年3月期から決算に反映しろと言われても、あまりに急な展開であり、準備も追いつかない。
例えば、融資先への支援を継続するか、支援先をどう整理するかも急ぎ検討する必要があった。このため、1998年3月期決算においては、大手銀行18行中14行(長銀、日債銀を除く)が、旧基準を用いていた。
このことからも、新会計基準が実態として唯一の公正な会計慣行として定着していたとは言えない。さらに、税効果会計も未導入であった。これは企業会計と税務会計のズレを調整する重要な会計ルールである。これが何の議論もなく、未導入のまま放置されていた。
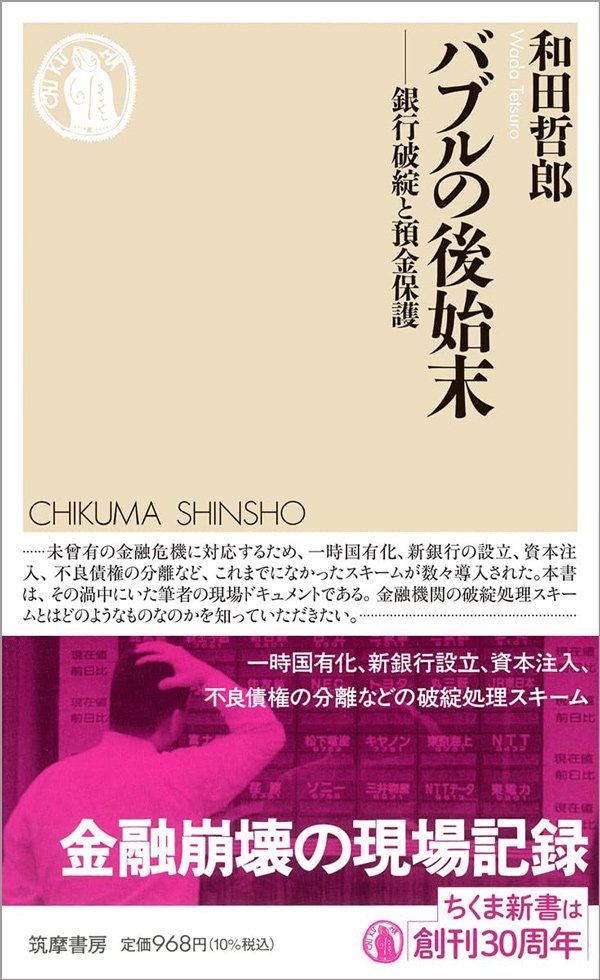 『バブルの後始末――銀行破綻と預金保護』(和田哲郎、筑摩書房)
『バブルの後始末――銀行破綻と預金保護』(和田哲郎、筑摩書房)
第3に、本当の経営責任は誰にあるのか、という問題である。捜査当局は最後の経営陣を粉飾決算容疑で逮捕し、司法当局は一審、二審で有罪判決を下した。真に経営責任を負うべき戦犯が誰かは、周知のことであった。破綻処理には多額の税金が投入される。しかし時効はわずか5年であり、これでは短かすぎないか。加えて、「真の戦犯」の代わりに現経営陣を粉飾で逮捕するというのは、国民を欺くことになりはしないのか。
この種の重い経営責任の時効については、多額の公的資金を投入していることもあり国民負担の観点から期間等を含め何がしかの検討、議論があってしかるべきと思われる。







