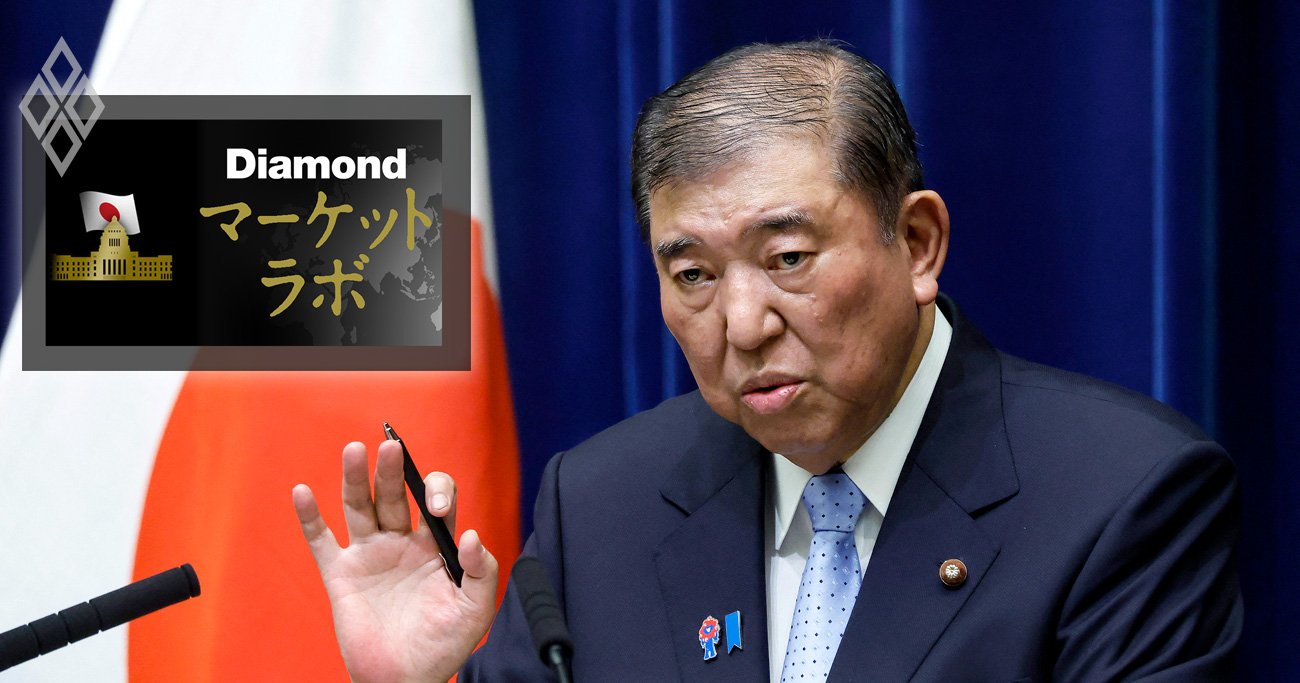 Photo:AFP=JIJI
Photo:AFP=JIJI
「実質賃金毎年1%上昇」は可能か?
コロナ禍前に戻すだけで3年必要
6月13日に閣議決定された政府の「経済財政運営と改革の基本方針2025」(いわゆる骨太の方針)は、「賃上げこそが成長戦略の要」という考え方を打ち出している。
目標は2029年度までの5年間で、日本経済全体で年1%程度の実質賃金上昇を定着させることだ。
賃上げが重要であることは論をまたない。今の日本経済の停滞感は、個人消費がほとんど増えないことにある。個人消費が増えないのは、実質賃金が低下しているからだ。
実質賃金には複数の計算方法があるが、連続性の点で相対的に優れる「共通事業所ベース」の名目賃金と、概念的な整合性があり実感にも近い「持家の帰属家賃を除く総合ベース」の消費者物価を使って計算すると、24年度の実質賃金はコロナ禍前の19年度に比べて3%近くも低い。
25年度以降、仮に実質賃金が毎年1%上昇したとしても、コロナ禍前の水準に戻すだけで3年かかるのだ。
そのぐらい今の実質賃金は落ち込んでいるのだから、政府が実質賃金上昇の重要性を強調するのは理解できる。しかし、問題が二つある。
第一に、賃上げの手段として念頭に置かれているのは、価格転嫁・取引の適正化、省力化投資などによる生産性の引き上げ、事業承継・M&Aの促進など、小粒かつ以前から行われているメニューの寄せ集めだ。
実質賃金1%上昇の定着というのはきわめて野心的な目標であり、本気でそれを目指すなら劇的な政策転換が必要だ。
第二に、賃上げは民間が決めるものであり、その賃上げを「起点」として経済成長を実現するという考え方が、政府の成長戦略としてふさわしいのかどうかだ。
現実には、経済成長が弱いから実質賃金が上がらない、という面も大きい。政府の成長戦略なら、経済成長を高めるために政府にしかできない政策を前面に押し出すべきだろう。







