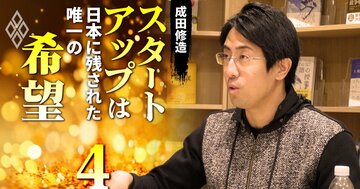これは私の推測ですが、この生徒はAOで慶應に受かったら慶應へ、落ちたらプロへ行こう、程度に思っていて、本気で大学で研究する気はないことを慶應の先生方が見抜いたのだと思います。
プロに行けるような実力と実績があっても、一次の書類審査で落ちるケースもあるのが、このSFCのAO入試の興味深いところで、要は「研究者としての資質があるか」が大切なのです。ここを間違えると、どんなに実績がある子も落ちやすいのです。
総合型選抜の試験とは、受験生の多様な才能や経験を評価するもの。自己アピールや面接、小論文などで、各大学が教育理念や研究分野に合った学生を選ぶ。総合型選抜を行う難関校・人気校はまず、慶応SFCの環境情報学部と総合政策学部の2学部が挙げられる。また、慶応法学部では「fit入試」という受験生の個性やポテンシャルを評価する入試がある。その他、早稲田大学では、創造理工学部建築学科で「創成入試」と呼ばれる総合型選抜が実施されている。また、スポーツ科学部でも総合型選抜が採用されており、特に「総合型選抜III群(スポーツ自己推薦入試)」では、競技能力に加えて、スポーツを科学的に探究する力も問われる。国立大学で全国的に有名な総合型選抜実施校は筑波大学で、「AC入試」と呼ばれている。
――「研究者としての資質があるか」とは、どういう意味ですか?
当たり前の話ですが、大学は研究をする場所です。部活を強くするところでも、青春をするところでもありません。特にSFCの場合は、「日本初」「日本で唯一」のような、ユニークな研究テーマが好まれる傾向があります。なので、慶應のAO入試は不合格だったけれど、一般入試で東京大学や東京工業大学(24年10月から東京科学大学)に受かった子も実際にいます。
SFCは募集要項で、自己アピールの基準目安を明らかにしています。その中に、「関心や興味を持ったテーマに関して自由研究や自主学習などの自発的な取り組みを開始し、成果を上げている」という項目があります。これは学校での探究活動でもいいし、課外活動でもいいのです。
私はよく、「高校3年生ではなく、大学0年生のつもりで研究しよう」と生徒に伝えています。高校生の探究と大学生の研究の狭間にある、“途中式”をきちんと評価してくれる傾向がSFC、筑波、立教など難関大のAO入試にはあると思います。