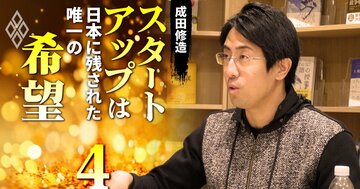よく学校の探究学習では、社会課題の解決につながることを前提にする活動もありますが、私は逆に安直な発想だと思います。率直に言えば、探究のテーマは、「推し活」の延長でもいいのです。ただし、単なる推し活ではなく、どれだけ沼る(深みにハマる)ことができるか。普通のファンやマニアと違って、いかに自分独自のものがあるか、熱量がどれだけあるかといったことが大事なのです。
私が指導した生徒の例ですが、出会った当初は美術教育を研究テーマにしていました。が、本心では、創作そのものが好きで、将来はブランドデザインなどクリエイティブな仕事に就きたいと思っていました。だから美術大学よりも幅広く学べそうな慶應SFCを志望したのですが、「合格するためだけの」志望理由を書いていたのです。
違和感を覚えた私は、彼女の興味の本質を深掘りするため、なぜデザインが好きなのか、どのような作品や工夫に魅力を感じるのか、本音を詳しく問診していきました。すると、ファッションのブランディングや色の組み合わせの話が止まらなくなり、「タータンチェック」へと展開しました。
タータンチェック(tartan)は、スコットランドの伝統的なパターンであり、日本でいう家紋のような意味合いも持つ「マークの要素」が強いとされます。彼女はこのテーマでリサーチを進めるうちに、どんどん熱中し、自ら図案を作成するなど検証するようになりました。そして最終的にSFCと筑波、両校に合格し、進学後はイギリス留学も果たしています。
――子どもが自ら上手にテーマを見つける方法は、あるのでしょうか?
テーマに良い・悪いはありません。ただ、社会課題の解決ありきになってしまうと、本質的な課題の発見まで至らずに、空想のアイディアで終わってしまいます。
例えば、SDGsの時代だからカンボジアに学校を建てたい、といった研究テーマや志望理由を毎年、一定数目にします。高校生でその実現が無理そうなら、「今の自分にできる教育支援とは何か」まで踏み込んで考えないといけないのです。
個人的には、「愛」か「怒り」からしか研究は生まれないと思っています。「これが好き過ぎて突き詰めたらすごく面白い発見がありました」「こういうものが許せないです。こういう社会を何とか変えたいんです」といった感情です。
ただし、怒りから始まる探究学習や研究は、リサーチ対象がネガティブになりがちなので、受験生自身がつらくなってしまうのが難点です。例えば虐待とか、動物殺処分とか。過去にはネグレクトを調べすぎて、精神的に疲れて鬱状態になってしまい、ドクターストップになった子もいました。
そういう意味では、愛から始める方が精神衛生上はいいでしょうね。愛の中にも「こう変えたい」「ここを改善したい」という視点があると、より深い研究になります。
まるで親が子どもに注ぐような愛情で、自分のテーマに向き合ってみる。そんな姿勢が、深みのある研究になり、総合型選抜で他の受験者に差を付け、結果として合格につながるでしょう。