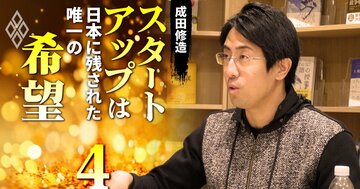――“途中式”とはどういうものですか?
何らかの探究や創作のプロセスを経て、コンテストや学会の発表に応募しただけでも、成果として見なされることがよくあります。「仮説を持って探究学習をした結果、これは今の高校生の自分には出来ないということが分かった」も成果なのです。
挑戦したけれど、失敗してしまった、あるいは成功しにくいことが分かった、も成果。それらを資料にきちんとまとめていれば、入賞経験に関係なく、書類通過の可能性が高まります。
例えばですが、スポーツで実績があったのに書類で落ちた子の場合、どうすれば良かったのか。それほど実績を出せる人物だったら、きっと成功までの途中で、普通の人では想像できないトレーニングや自己分析があったはずです。それは筋肉の勉強かもしれないし、栄養の勉強かもしれない。その“途中式”をきちんと資料にすれば、途端に研究成果となります。今まではこのスポーツをずっとやってきたけれど、次はその経験をもとに大学ではこんな研究をしたい、というように「過去・現在・未来」をつなげるイメージです。
――研究テーマが見つからない場合は、どうすればいいのでしょうか?
周りの大人が質問してあげるのも手です。まずは今、何が好きかを聞く。そして、これまで何が好きだったかを聞いて過去の整理をし、さらに将来どうなりたいのかを聞きます。
もちろん、これらが全くつながってないケースもあります。その場合、それぞれ具体化と抽象化を行き来しながら、キーワードを変換していきます。過去と未来がつながる接点が1個でも見つかれば、立派な志望理由になります。
もし今、高校3年生だったら出願時期の夏までに出来る活動を増やし、出願ギリギリまで自主研究を重ねていくのがいいでしょう。逆に、早々に志望理由を書き終えてしまう人の方が危ないです。