結局、そのバックアップになるだけの火力発電も必要になってしまうんです。脱炭素とは逆行する動きになってしまいますよね。
また、再生可能エネルギーについては現状、コストがかかり、電気代が高騰する問題があります。ロシアがウクライナに侵攻したことを受け、ドイツはロシアの天然ガスへの依存から脱却するため、再生可能エネルギーの割合を増やすことを決めました。
2023年には原発も止めてしまったので、これから電気代がおそらく高騰していくと思われます。
日本も2024年2月現在、電気代が大変なことになっています。これはなぜかと言えば、火力発電の燃料の値段が上がったから。そして、その価格高騰をうまく吸収できなかったのは、原子力発電を止めているからです。
これは、最適解を見つけるのがとても難しいテーマです。
それらしいデータに
すぐ飛びつかないこと
深く背景まで考えるという意味では、ドイツの脱原発は本当にいい例です。
ドイツは電気の輸出で儲けつつ、脱原発、きれいなエネルギー政策のアピールをしています。でも実は、とくにフランスの原子力発電をセーフティネットとして使っているし、火力発電の割合もなかなか減りません。かなり巧妙な広報活動です。
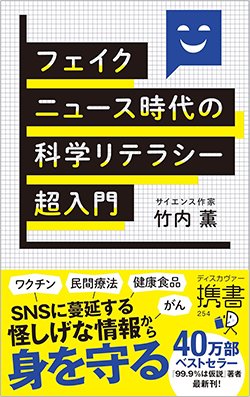 『フェイクニュース時代の科学リテラシー超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、ディスカヴァー携書)
『フェイクニュース時代の科学リテラシー超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、ディスカヴァー携書)竹内 薫 著
フランスからしたらふざけるなという気持ちでしょうね。フランスでは7割近くを原子力発電で賄っていますが、ドイツは「フランスの電気は汚い、自分たちの電気はきれいだ」と触れ回っているわけですから。
さてここまで、科学は万能ではないというテーマから、科学にだってわからないことや限界はある、そのリスクのバランスをうまくとって考えようという話をしてきました。
ここでお伝えしたいのは、深掘りをして考えていくことの重要性です。それらしいデータがあっても、短絡的に飛びつかない。データがあるといろいろな人がいろいろなことを言いますが、本当にそうなのかなと、自分で考えてみましょう。
データを知っているだけでは意味がなくて、それを踏まえて科学的な視点で考えようとするくせが、科学的な思考力につながるのです。







