母が41歳のとき、父が他界しました。残された5人の子どもを、母は女手一つで育ててくれました。小さな畑で野菜を育て、夜遅くまで手内職に明け暮れていました。それは、貧しい生活でした。
そんな母がいつも言っていた口癖があります。「仕方なかんべさ」「何とかなるべさ」「あの人はたいしたもんだ」。この3つの言葉が私の心に染み込んでいます。自分の境遇を恨んだりするのではなく、いつも前向きに生きようとする。決して人の悪口を言うことなく、常に一人ひとりのすばらしい面に目を向ける。
母は田舎の農家の娘でした。大した教養があるわけではありません。それでも母のこの言葉は、いかなる哲学者の言葉よりも、私にとってはすばらしいもの。それは今でも自分の人生の原点であり、指針とも言うべき教えとなっています。
親子にとって大切なのは
「心の習慣」を伝えること
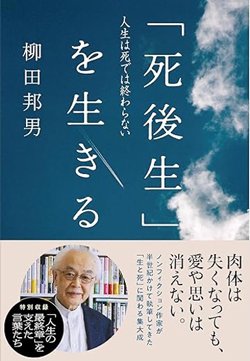 『「死後生」を生きる 人生は死では終わらない』(文藝春秋)
『「死後生」を生きる 人生は死では終わらない』(文藝春秋)柳田邦男 著
こうした親から受け継がれる心の持ち方や言葉を、私は「心の習慣」と呼んでいます。それこそが大事な「家族の文化」です。高価な物を子どもに与えるのではなく、人生の指針となる心を伝える。欲望や幸福にばかり目を向けるのではなく、しっかりと悲しみや辛さを見つめる勇気を教える。それが親としての役割ではないでしょうか。不幸を知らない子どもたちは、決して本当の幸せをつかめない。
今は子育てに悩む母親が増えているようです。何十万人もの母親が、インターネット上で悩みを打ち明け合っている。彼女たちはパソコンを扱う知識を持っている。パソコンを買うお金も持っている。そしてパソコンを置くきれいな部屋も持っている。なのに子どもを育てることに悩んでいる。何とも奇妙な話だと思います。家族の文化が壊れた大変な時代です。
何か大切なものを忘れてはいないでしょうか。人間にとって、何が1番大切なのか。そのことを、本気で考える時期に来ている。自分の境遇を恨んでばかりいるのではなく、たくさんの不幸にしっかりと目を向ける。そこから温かな「心の習慣」を生み出していく。大切なのは、親と子が一緒になって、幸せのかけらを探していくことです。







