人を癒やすロボットは
役に立っていないのか?
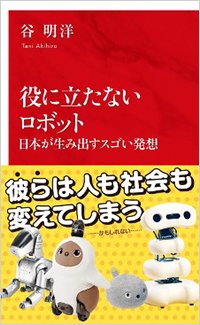 『役に立たないロボット 日本が生み出すスゴい発想』(インターナショナル新書)
『役に立たないロボット 日本が生み出すスゴい発想』(インターナショナル新書)谷明洋 著
身体に触れられたときに優しく反応することで癒し効果を発揮する、セラピーロボット「パロ」はどうだろう。東日本大震災の被災地施設で活躍した実績もあるし、筆者も仕事がうまくいかないときに、展示フロアで「パロ」を抱きかかえて紹介しながら、結果として自分も癒されたように感じた経験がある。ペットの代替として多くの人に愛されてきた「アイボ」もまた然り。
これらのロボットは「アシモ」やアンドロイドと異なり、私たちの日常生活の中で「役に立っている」ようにも感じられる。
ところがあらためて、『ロボットは友だちになれるか 日本人と機械のふしぎな関係』(NTT出版 2011年)を読んでいくと、著者にして「アイボ」の構想にも関わったフレデリック・カプラン氏は当時を振り返りながら次のように述べている。
エンタテインメント・ロボット、つまり役に立たないロボット、何らかのサービスを提供するのではなく、ただただ存在し、気に入られ、自律していることだけを役目とするロボット、そして、いつか人間がそのような機械と情動的な関係、さらに相互的な関係を築けるなどという考えは、わたしが出会った人の多くには想像もつかないものだった。
おそらく欧米では一般的なのであろうこの価値観からすると、「パロ」もロボットとして「役に立たない」「サービスを提供するのではない」ということになる。
いったい「役に立たない」とは、どういうロボットに使うべき言葉なのだろうか。







