『桃太郎』の話をしながら途中で忘れてしまう「トーキング・ボーンズ」は、分かりやすい。流暢ではないしゃべりで危なっかしさを醸し出しておいて、「どんぶらこ、どーんぶらこと…、えーと……なにがながれてきたんだっけ」と話の続きを思い出せないことを素直に開示するから、子どもたちは面白がって「桃!」と反応するのだ。
また、しゃべる機能を持たない「ゴミ箱ロボット」であれば、困っていることを「察してもらう」必要がある。常にヨタヨタして、「このロボットは何をしたいのだろう?」と周りの人の注意を引き、さらにゴミに近づいて激しくキョロキョロ、モジモジして見せるという二段構えの作戦で、「ゴミをなんとかしたいけど、自分ではできない」という状況を伝える。
いずれにしても、ロボットが「弱さ」を活かすためには、ヨタヨタ感によって「心や意思を感じてもらう」だけでは不十分だ。ヨタヨタ感は「何をしてほしいのか」を察してもらうための布石にすぎなかったのである。
「弱いロボット」のモチーフが
ゴミ箱や骨の理由
ロボットの見た目についても、岡田さんに尋ねてみる。どうして「弱いロボット」のモチーフがゴミ箱や骨なのだろう。どうしてこんなに頼りなくつくられているのだろう。
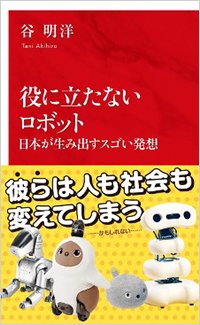 『役に立たないロボット 日本が生み出すスゴい発想』(インターナショナル新書)
『役に立たないロボット 日本が生み出すスゴい発想』(インターナショナル新書)谷明洋 著
実体を持っていることは、見る人の志向的な構えを引き出すうえですごく重要なのですが、その体が人間に似すぎると、見る人からは「人間のような能力を持っているんじゃないか」と期待されてしまうんです。すると、多少のことができたくらいでは「たいしたことないじゃないか」とがっかりされてしまう。期待値とのギャップですよね。
もしも、精悍(せいかん)な若者の顔をした人間そっくりのロボットが、ヨタヨタとゴミの近くまで歩いてきてモジモジし始めたとしたら、どんなことを感じるだろうか。さらに、ゴミを拾ってあげたことに対して、その精悍な顔ですごく嬉しそうな反応を示されたとしたらどうだろう。かなりの違和感を覚えるはずだ。
生き物らしさを感じさせる身体が必要でありながら、リアルな生き物に近づけると期待値が上がり過ぎてしまう。そのジレンマを回避するための策が、ゴミ箱や骨をモチーフとした頼りない見た目なのだった。







