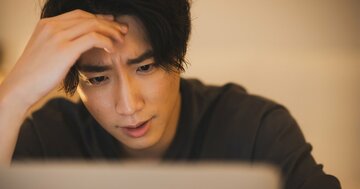アイデアが出てこないと悩む人の多くは、こうしたアイデアを生み出すための材料を全く用意せずに目を閉じて脳裏にアイデアが自動的に生み出されるのを待っています。この過程で、多くの人は本筋から外れて脱線してしまいがちです。特にワーキングメモリが弱い人はこうなりやすいと言われています。
ワーキングメモリとは、たとえば宿泊するホテルのフロントで聞いた部屋番号を記憶しながら部屋まで移動するときに用いるような、一時的な記憶を指します。
このワーキングメモリが弱いと、タスクにとりかかるときにはA→B→Cの順にこなすぞと決意しながらも、作業を進めるうちに忘れてしまい、A→C→予定にないDへと脱線したり、A→A'→A''のように深掘りしすぎて迷子になることもあります。
ナナさんは、ワーキングメモリの弱さが原因で脱線が多くなり、全体像を把握しづらくなっています。そのため、何から始めてよいかわからず、途中で迷子になりがちのようです。
解決策は完成予想図を
見える化すること
企画を考えるといったアイデアを早めに生み出すには、参考資料のような既存の資料に目を通しながら、最初にアイデアの元を集めたり、それらを組み合わせてみたり、「今回の企画の目的は」と枠組みを整理してみたりすることが大切なのです。
また、ワーキングメモリの弱さを補うために、完成予想図や視覚化した計画表、「やることリスト」を手元に置きます。迷子になったり脱線しそうになるたびに、現在地を確認できるからです。
まず、似た企画書を手元に置き、全体像を見える化することから始めましょう。
具体的には、完成予想図を描いて、それをナビにして目次を作ります。次に、各セクションごとに必要な情報を箇条書きにして整理します。これにより、迷子にならずにスムーズに資料を作成することができます。