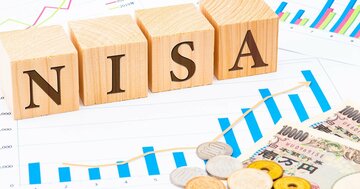金融庁の報告書では不足額が1300万~2000万円と計算していましたが、高齢夫婦世帯は不足額以上の貯金を持っているというわけです。家計調査通りであれば、「老後2000万円問題」なんて最初からなかったのです。
「そうは言っても、平均的には支出が収入を上回っているのは事実なのだから、貯金がない人は生活できないのでは?」という質問に対しては、「貯蓄がある人を含めた平均の支出を示しているから、みんなが同じ支出をしているわけではない」が回答になります。
当たり前のことですが、生活水準は人によって変わります。貯蓄のある人が多めの支出をしていれば全体の平均は上がります。私の祖母は年金暮らしでしたが、基本的に年金収入で生活するようにしていました。当時の物価だからできたこととは言え、収入に合わせた生活をしているという高齢者は多いのではないでしょうか。
報告書に使われたのは
実態とかけ離れた過大な数字
もう1つの問題は、2017年の単年の家計調査の結果を利用している点です。家計調査は定期的に行われているのですが、2022年の結果では、収入と支出の差は2万2000円です。なんと、5万5000円ではないのです!
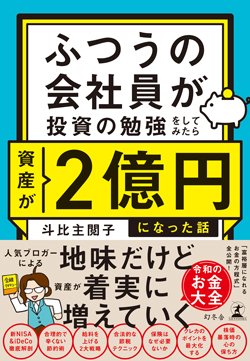 『ふつうの会社員が投資の勉強をしてみたら資産が2億円になった話』(斗比主閲子、幻冬舎)
『ふつうの会社員が投資の勉強をしてみたら資産が2億円になった話』(斗比主閲子、幻冬舎)
たまたま2022年は低い数字だったのかと思い、他の年度も調べてみました。2021年は1万8000円、2020年不足額なし(黒字1000円。コロナの給付金の影響あり)、2019年2万7000円、2018年4万1000円、2016年3万6000円と、どの年度も5万5000円を下回っています。
とすると、2017年の収支の差額である5万5000円を利用して老後の不足金額を計算しているのは、実態に即しておらず、過大な数字になっている可能性があります。
なぜこんなに欠陥のある分析をしたか今となっては分かりませんが、恐らく、金融庁として国民の資産形成を促す新制度を導入したいという目論見があり(結果、新NISAが誕生しました)、あえて不足額が多めになるような数字を示したのではないかと邪推します。
いずれにしても、あれだけ大騒ぎした「老後2000万円」という数字は、あまり意味がなかったわけです。