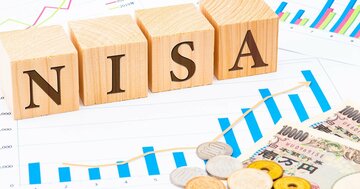労働者であるかぎり
資産家には追いつけない
この現象を学術的に研究し発表したのが、フランスの経済学者トマ・ピケティの『21世紀の資本』(みすず書房)です。トマ・ピケティが18世紀まで遡ってデータを分析したところ、投資をした時の利回り(r)が年間5%程度であるのに対し、賃金の上昇率(g)は年間1~2%でしかなかったということです。上昇率は大なり小なり国や時期によって変わるものの、投資の利回りが賃金上昇率を上回る「r>g」という不等式は、基本的にはいつでもどこでも成り立っているということが指摘されています。つまり、労働で賃金を得て富を築いても、お金持ちがすでにある資産を投資に回し続ける限り、労働者はお金持ちにいつまでも追いつけません。
トマ・ピケティは、このままの不等式が続けば、世界ではいずれ中間層がいなくなり、格差が拡大していくことから、政策的な対応が必要としています。本研究の影響ゆえか、世界的なトレンドとして、節税目的で税金が少ない国に資産を移すことを厳しく制限したり、株式の売却時や相続時の税金を増やすという政策は行われているものの、格差の拡大を止める抜本的な効果は乏しいのが実態です。要するに国の対策を待っていても、限界があります。
石川啄木の「はたらけどはたらけど猶わが生活(くらし)楽にならざり」ではないですが、では、資産家が豊かになり続け、労働者はギリギリの生活を営まないといけない中で、私たち労働者はどうすればいいでしょうか。答えは、身も蓋もないですが、自分も早く資産家になることです。
旧NISAは国民の1割程度にしか浸透しませんでしたが、新NISAの使い勝手の良さからすればさらに多くの人が投資を始めるはずです。
新NISAの投資枠1800万円は老後の資産形成には十分な金額です。それどころか、1800万円も投資できたなら、10年後は無理でも20年後には富裕層の仲間入りをする人が続出するはず。
非常に残念で悲しいことですが、賃金労働者でいる限りは、いつまでも豊かな生活は望めません。収入を増やし、支出を減らし、余った貯蓄で投資を行うことが、労働者から資産家になるための分水嶺(ぶんすいれい)となります。