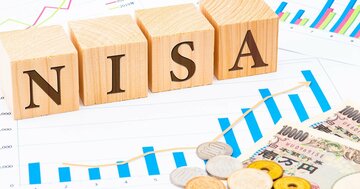政策に敏感になれば
かくれ増税に気付く
金融リテラシーが高まり、資産が増えてくると、政策への興味が増します。
例えば、手取りを増やそうと給与明細をまじまじと見ていれば、社会保険料が近年“増税”されていることを否が応でも分かると思います。老後の生活をシミュレーションしていたら「75歳以上の後期高齢者の医療費負担が1割から2割に増える」というニュースは気になるはず。
他にも、退職金計算をしようとすると、現在の退職所得控除は長い期間(20年超)同じ企業で働く人に有利にできているので、一律40万円×勤続年数にしようという改正が議論されていることが目に入ってくるはず。
他にもお得な節税制度である、ふるさと納税、新NISA、iDeCoも同様です。制度を利用していればこそ、改善・改悪への意識が高まります。
知らない人も多いと思いますが、日本では毎年税制改正が行われています。
2024年1月から開始された2023年度の税制改正では、新NISAの導入以外に、相続時精算課税贈与で毎年110万円の贈与が相続税の課税対象から除外、暦年課税贈与が相続とみなされる期間が「死亡前3年以内」から「死亡前7年以内」に延長、教育費や結婚資金の一定金額以下の贈与が非課税となる制度の延長など、高齢者から若年層への資産移転を促す改正が実施されました。
一方、いわゆるタワマン節税が封じられました。タワマン節税とは、相続時に例えば1億円の現金はそのまま1億円として評価されるのに対し、不動産であれば7割の7000万円、タワマンだと3割の3000万円程度しか評価されないことを利用して、お金持ちが死ぬ前にタワマン(特に高層域)を購入し、相続税を抑える手法です。実際のタワマンはともすれば現金以上の価値があるわけで、これを問題視した国税庁が改正に動いたわけです。
日本では高齢富裕層から若年層にいかに資産を移転するかが課題となっており、最近はこの手の税制改正が増えています。