チーム全体としても「同じ部分」と「違う部分」によって構成されているのです。
「チームで1つになる」という表現がよく使われていますが、その意味は「みんなが同じようになる」ということではありません。「1つになる」という表現より、「一体感をつくり出す」の方が正しいと言えます。
それは、違いを受け入れながら共通点を見つけ、共存を図ることにあります。それを可能にするのは、一人一人が主体的にチームへ関与することです。
ただただ「違う人たちが集まっているだけ」であれば、見かけだけの多様性にすぎません。本当の多様性(Diversity)は、違いを認め合い、それが有機的に機能してはじめて「包含(Inclusion)」の状態を生み出します。
共有を行う上で必要なのは
「同意」ではなく「理解」
多様性と包含(Diversity and Inclusion,D&I)という考え方はすでに広く知られていますが、単に障がいや国籍、性別などの見た目の違いだけでなく、チームが機能するためには「同じ部分」と「違い」を共有する力が求められます。そして、それを可能にするのは非認知的な思考を持つ人材の存在です。
共有を行う上では、他者と関係を築く際に非認知的思考を持っていないといけません。その1つは「同意」より「理解」の接し方ができることです。
認知的な同意の「Agree思考」では、他者に対して「同意できるか否か」の2択しかありません。「考えが同じでなければいけない」ことに囚われると、相手に同じ意見を強要したり、反対意見を否定したりする結果になってしまいます。
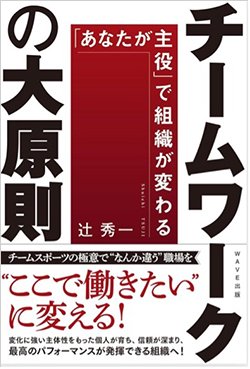 『チームワークの大原則「あなたが主役」で組織が変わる』(辻 秀一、WAVE出版)
『チームワークの大原則「あなたが主役」で組織が変わる』(辻 秀一、WAVE出版)
認知的な脳はこのような「同調性」を求める傾向が強く、「同じ」であることが正しいと考えます。しかし実際は、感情も考えも人の数だけ違うわけで、まずはそのことを理解する。
「Understand思考」を持つことで、質の高いコミュニケーションが生まれるでしょう。
「同意」より「理解」を重視するスタンスは、人間関係の中で自分自身をフロー(編集部注/集中し、没頭している状態を維持すること)に保ちやすいばかりか、周りにも「わかってもらえた」という自己存在感を与え、結果的にお互いがフロー状態に近づくことができます。
これがチーム内で実現すれば、違いを理由に否定し合うことなく、互いに機能的な関係を築くことができるのです。







