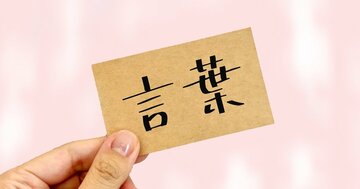たとえば電車内で「携帯電話の使用はご遠慮ください」と言われたとき、聞き手の年代によって解釈が違ってきます。「電話」と聞けば「話すもの」と考える高齢者から、LINEやゲームや動画観賞のイメージが先に来る高校生までいろいろです。
先日の帰宅時、恐らくスマホでゲームをしていたと思われる高校生2人が「携帯電話の使用はご遠慮ください」のアナウンスを聞いて、「やめたほうがいいのかな?」「話さなけりゃ、いいんじゃない?」とけげんそうでした。
医療機器の誤動作を防ぐため、病院同様に携帯電話の電源を切ることを求めているのか、それとも、空いている車内ではメールやゲームだけならOKなのか、迷わないようにアナウンスを工夫している路線もあります。しかし、曖昧なアナウンスを流している路線もまだ多いようです。
「ご理解とご協力をお願いします」とアナウンスされても内容を「ご理解」できないので「ご協力」のしようがないわけです。
その一方では「降りる方がすんでから、前の方から順にご乗車ください」などの親切過ぎる(?)アナウンスを聞くこともあります。
再確認させている、という発想かもしれませんが、ムダな気もします。ムダなアナウンスは、他のもっと重要なアナウンスを認識させる妨げになりかねません。
パソコンの警告文は
例外なしで分かりにくい
私にとってパソコンは、会社の仕事でも執筆でも文房具として欠かせません。たった今も、パソコンのキーボードを叩いています。
しかしパソコンを使う誰もが経験するとおり、時々突然、何かの警告、あるいは「はい」「いいえ」の選択を迫る文が表示されることがあります。この説明文は、ほとんど例外なしに、何を言っているのかまったく理解することができません。
メッセージの形式や内容はさまざまです。