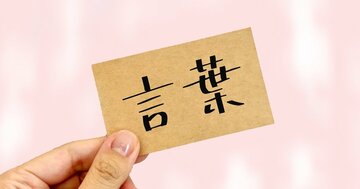いずれも説明術の基本中の基本です。
さて本番までの1週間に、さらに予行演習を2回させました。たった3つのアドバイスに従っただけで、部下のプレゼン術の向上には目を見張るものがありました。
1回目の予行演習は20点ほどでしたが、この3点を意識した2回目は60点になりました。
さらに練習を重ねて臨んだ3回目のリハーサルは80点でした。そして本番でのプレゼンは、ほぼ100点満点になったのです。
私の持論である「分かりやすい説明は誰でもできる」は実証されたのです。
世の中に溢れかえる
「分かりにくい説明」
このように、「分かりやすい説明」をすることはけっしてむずかしくないはずなのに、世の中には分かりにくい説明があふれています。
現代社会には、円滑な情報の流れが不可欠です。そして情報が円滑に流れるためには、人々の意図がスムーズに通じ合わなくてはなりません。しかし実際に私たちの住む世界では、さまざまな「分かりにくい説明」のため、多くの人が首をかしげ、立ち止まり、とまどっています。
これを人体にたとえれば、情報の流れは血液の流れでしょう。健康にとって、血液がサラサラと流れることが大切であるのと同じです。血液ドロドロ状態では、動脈硬化、脳梗塞(こうそく)、心筋梗塞という深刻な事態に発展しかねません。
たとえば、電車内のアナウンスが分かりにくいと思ったことはないでしょうか。分かりにくい以前に、聞き取れない場合も多いと思います。アナウンスが乗客に危険を事前に知らせるような場合、それが伝わらなければ、時には乗客が危険にさらされることにもなりかねません。
アナウンスしている乗務員は、自分がマイクに向かって話していることが、まったく乗客に伝わっていないことに、気づいてさえいないのではないでしょうか。
電車内のアナウンスが分かりにくいのは、音量だけの問題ではありません。音量は十分なのに、乗務員がボソボソとつぶやくように話すため、聞き取りにくい場合もあります。アナウンサーのような発声は必要ないにしろ、内容が乗客に伝わるように話すことは最低限必要なはずです。
「何のために禁じているか」を
明確にしないアナウンス
また、言葉が聞き取れても、意味が曖昧な場合もあります。