天然うなぎのいる場所
天然うなぎの四大産地をあげると、湖沼では霞ヶ浦(茨城県)、琵琶湖(滋賀県)、三方五湖(福井県)、宍道湖(島根県)でしょう。河川では利根川、四万十川、球磨川、筑後川などがあります。現在も天然うなぎが日本各地に存在していることは確かですが、個体数は減少しています。
そもそもうなぎは、広大な海を泳ぎ回っている回遊魚です。産卵場所は、南太平洋のマリアナ諸島西方海域とわかりました。赤ちゃんうなぎは漂いながら、潮の流れに乗って、2000kmを旅して日本までやって来ます。回遊魚ですから当然のことですが、ものすごい距離を泳いでいるわけです。
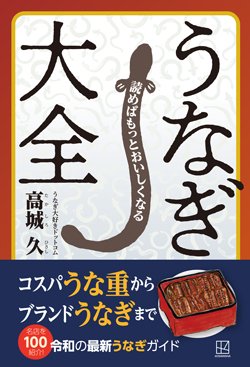 『読めばもっとおいしくなる うなぎ大全』(講談社)
『読めばもっとおいしくなる うなぎ大全』(講談社)高城 久 著
海から川に入り、餌が多く流れもゆるやかで、隠れるところもたくさんある河口付近に棲みます。環境としてうなぎに一番いい場所は、海の水と川の水が入りまじる汽水(きすい)です。ですから、浜名湖や宍道湖などの汽水湖には昔から天然うなぎが棲んでいました。そして、そこで棲み家を得られなかったうなぎは、新天地を求めて川をどんどん遡上(そじょう)していきます。うなぎが遡上するからこそ、利根川や四万十川などの川でも天然うなぎが捕れました。
日本における天然うなぎの漁獲量は、国立研究開発法人水産研究・教育機構の資料によると、第二次大戦などでの一時的な落ち込みはあるものの、1960年代までは3万トン程度でした。それが、1970年以降減少していきます。この頃は高度経済成長に乗ってダム、水門、河口堰などの人口構造物がたくさん建設された時期であり、河口付近でシラスウナギを捕って、人の手で育てる養鰻業が盛んになった時期でもあります。
愛知県や静岡県が近年行った調査では、川に遡上せず、海で過ごす「海うなぎ」が4割ほど、河口などの塩分の混ざった汽水域で過ごす「汽水うなぎ」が4割ほど、淡水で育った「川うなぎ」は2割ほどとのこと。うなぎが遡上しにくくなっていることは数字の上でも明らかです。さらに乱獲かくや河川環境の悪化、気候変動、海流の変動などさまざまな要因が重なり合って日本付近に回遊してくるシラスウナギの数そのものも減ってしまいました。
現在、天然うなぎは簡単には食べられません。価格も時価。平均で、専門店の通常のうな重の3倍から4倍程度です。食べたい方は、お店のウェブサイトやSNSなどをつぶさに見て、「天然うなぎ入荷」などの情報を探すしかありません。産地の近くは入荷しやすいので、うなぎ漁の時期に産地に行けば、運よく出会える機会もあるかもしれません。







