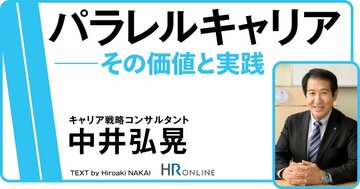“新しい「全員戦力化」”と連動する「人的資本経営」
“新しい「全員戦力化」”と連動するのが、「人的資本経営」だろう。きっかけは、2020年(令和2年)に公表された経済産業省の「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書」、いわゆる「人材版伊藤レポート」だ。経済産業省は、人的資本経営を「人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」と定義している。
「ヒト・モノ・カネ」といわれるように、従来、人材は経営資源のひとつと捉えられてきた。しかし、人材は日々の業務や研修などを通じて成長し、企業にとって価値創造の原動力となる。そこで、人材を「人的資本(Human Capital)」と捉え直し、人材マネジメントについても、「管理」から「投資」へと発想を転換しようというのだ。近年、上場企業では、「統合報告書」などで人的資本についてのさまざまな情報を開示する動きも広がっている。
守島 「人的資本経営」で押さえておかなければいけないのは、この議論は企業側から出てきたのではなく、投資家目線での経営ガバナンスに紐付いた問題提起であるという点です。
かつて、第二次産業中心の時代には、資金調達と設備投資が企業の最優先課題でした。それが、いまや、産業構造は大きく変わり、企業が生み出す価値の源泉が技術やアイデアになってきました。技術やアイデアを生み出すのは「人」です。しかも、将来へ向けて有望な市場ほど競争が激しく、専門的なスキルやノウハウを持つ専門人材が希少になります。
企業が中期経営計画で新規事業や新しいビジネスモデルを打ち出すと、「それを遂行するための適切な人材はいるのか? いないのであれば、どうやって確保するのか?」といったことが、投資家をはじめとした多くのステークホルダーから問われるようになっています。
「人的資本経営」という言葉にも注意が必要だろう。「資本」とは、教科書的にいえば、労働や土地とならぶ生産要素のひとつだ。また、企業会計では、貸借対照表(BS)において、「資産」から「負債」を差し引いた「自己資本」を指し、資本は「資金」というニュアンスが濃い。「人的資本」はあくまでも比喩的な表現であり、「人的資産」と言い換えることもできる。重要なことは、その他の「資本/資産」は企業が基本的にコントロールできるが、「人的資本/人的資産」は企業の思惑どおりにコントロールできるとは限らないことだ。
「人的資本/人的資産」は、実態としては従業員一人ひとりが持つ能力やスキル、意欲のことであり、従業員が企業に対して“出資”しているといったほうが適切かもしれない。
守島 かつて、日本企業における人的資本・人的資産の扱いは企業主導でした。「○○の部署へ配置転換する」「来期から□□支店へ行ってくれ」と言われた社員は、疑問をほとんど感じることなく従っていました。
しかし、昨今、そうした会社からの一方的な指示命令だけで、社員はなかなか動かなくなってきており、聞くふりをしつつ最低限のことしかしないような姿勢も見られます。近年、静かな退職(quiet quitting)と呼ばれ始めた現象です。
働く人が自分の意思で企業の戦略や事業に、自己が持つ資本を進んで投資するように、また、雇用側は、新たなスキルや知識を学んでくれるように働く人の背中を押さなければなりません。それが“新しい「全員戦力化」”が目指すべき方向です。