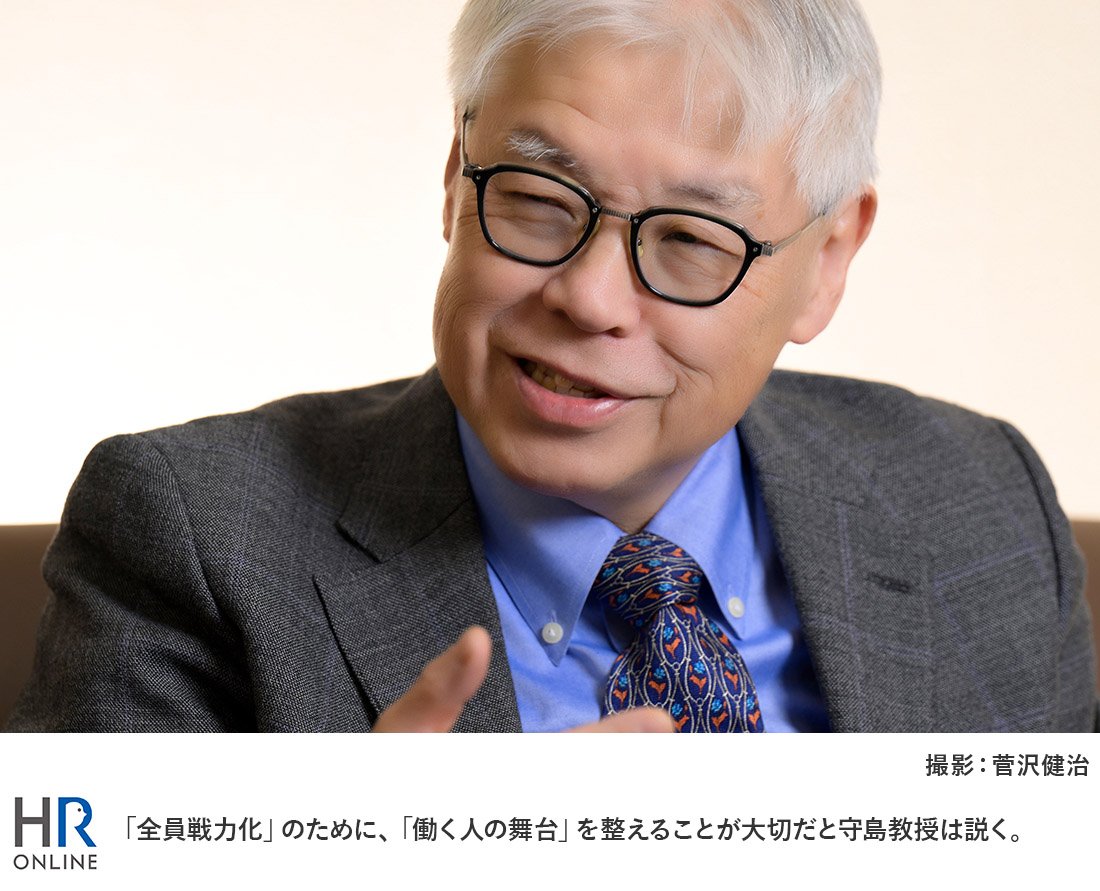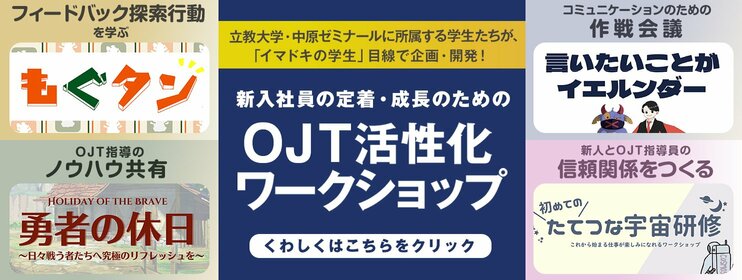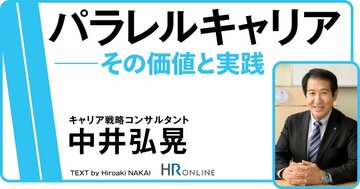“新しい「全員戦力化」”の実現のために必要なこと
“新しい「全員戦力化」”を目指すにあたって、人事制度などの整備はもちろん必要だが、それに加えて、「心理面がとりわけ重要になる」と守島教授は説く。具体的には、どのような点に注意すべきなのだろうか。
守島 ポイントをふたつ挙げておきます。
ひとつは、働く人は昔も今も給与水準や福利厚生を気にしますが、それと同時に、あるいはそれ以上に、特に若い世代は、その企業で働くことが「社会にとってどういう意味があるのか?」「どういう価値を提供しているのか?」に注目するようになっています。それに対する企業としての答えがパーパスやビジョンです。練り上げられたストーリーを踏まえたパーパスやビジョンを提示し、共感してもらうことがこれまで以上に重要になります。
もうひとつは、「働く人の舞台」を整えることです。各種データを見ると、日本の企業では、給与や雇用保障、福利厚生などの点で不満はなくても、「自分が所属する組織やチームから温かく受け入れられていない。サポートされていない」という感覚が強い傾向があります。どんなに優秀な人材も、周りが敵だらけの状態では、自らの人的資本・人的資産を、その企業に安心して投資すること、活かすことはありません。
これは日本だけのことではありません。アメリカのシリコンバレーで注目されている概念に「ビロンギング」というものがあります。これは所属を意味する“belong”が基になっており、自分の個性を大切にしながら気持ちよく組織に関与し、居場所があると感じられる状態のことです。契約や制度を整えるだけではなく、企業と社員の間に心理的な繋がりを育んでいかないと、エンゲージメント低下や転職などがおこり、人材コストばかりが上がり、事業の継続性にも支障が生じていくのです。
“新しい「全員戦力化」”においては、社員が自らの人的資本/人的資産のパフォーマンスを最大限に発揮したいと思うようになることが重要だが、一方で、企業は、多様化する社員の事情やニーズのすべてに対応することが難しいようだ。
守島 ただ、企業側としては、当然、あるところで一線を引く必要があります。例えば、ワークライフバランス重視で「週半分以上の在宅勤務」を希望する人に対し、事業内容や業務条件から週1日しか認められない場合、「週半分以上の在宅勤務」は不可能となります。
企業経営は、基本的に「この指とまれ!」です。自社のパーパスやビジョン、ビジネスモデル、業務内容に少なくとも納得する人を集めることをベースにしつつ、入社後は、持てる能力や知識を最大限に発揮してもらう。そのバランスこそが“新しい「全員戦力化」”につながると思います。