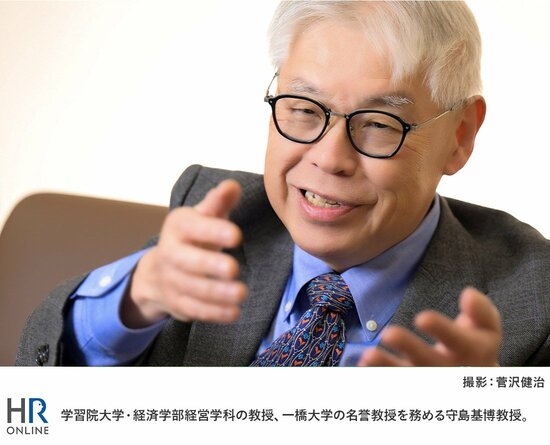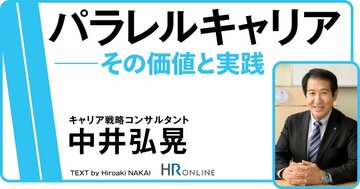VUCA(*)が巷間に流布して久しいが、国内では出生数が70万人を切り、海外ではトランプ関税に加え、地政学リスクが高まるなど、不確実性がいっそう深まっている。こうした状況は企業の人事戦略にも大きなインパクトをもたらし、黒字ながらも人員整理に着手したり、新卒採用数を見直したりする動きがある。これは、人事部門が、「人事制度の管理者」から「人材戦略の司令塔」への役割転換を迫られていることに通じるだろう。その役割転換について、人的資源管理論を専門とし、政府の各種審議会委員なども歴任してきた守島基博教授(学習院大学経済学部教授/一橋大学名誉教授)へのインタビューを通して考えてみる。(ダイヤモンド社 人材開発編集部、撮影/菅沢健治)
*volatility(変動性)、uncertainty(不確実性)、complexity(複雑性)、ambiguity(曖昧性)の頭文字をつなげた現代社会の特徴を示すキーワード。「ブーカ」と発音する。
昔も今も、企業経営の基本は「全員戦力化」にある
さまざまな「業務自動化」が進んでいるとはいえ、いまなお、企業の現場を担うのは「人」だ。ところが、2024年に日本の出生数は国の想定より14年も早く、年間70万人を切った。約20年前(2003年)の出生数が112万人だったので、そこから4割近い減少になっている。今後、「人手」の確保に苦労する企業が加速度的に増えることが推測されるが、より深刻なのは、「人材」不足であると守島教授は指摘する。
守島 人材不足とは、企業が自社の経営戦略やビジネスモデルを展開するために必要な人材が充足できない状態を指します。例えば、DX(デジタルトランスフォーメーション)においては、業務のデジタル化に加え、生成AIも現場に浸透してきており、ITやAIのスキルを備えた人材は業種を問わずに引く手あまたです。また、トランプ関税の問題はあるにしろ、中小企業を含め、多くの日本企業は、今後いっそう、世界市場に打って出ていく必要があり、グローバル人材が欠かせません。
しかし、現有の人材を、必要な人材にそのままシフトさせることは困難で、人材のミスマッチによって、余剰人材さえ生まれています。さらに、この20年ほどで、育児や介護を働きながらする人、高齢者、非正規雇用者、外国人といった人材の多様性が急速に高まっています。さらに、多様な人材はそれぞれの事情やニーズを抱えており、経営層や人事部門、職場の上司が一人ひとりにきめ細かく寄り添わなければ離職につながります。そうしたことが、人材不足に拍車をかけています。

守島基博 Motohiro MORISHIMA
学習院大学 経済学部経営学科教授
一橋大学 名誉教授
1980年、慶應義塾大学卒業。86年、米国イリノイ大学産業労使関係研究所博士課程修了。カナダ国サイモン・フレーザー大学経営学部助教授、慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授・教授、一橋大学大学院商学研究科教授を経て、2017年より現職、2020年より一橋大学名誉教授。専門は人的資源管理論・組織行動論。政府の審議会委員なども兼務。『人材マネジメント入門』『全員戦力化 戦略人材不足と組織力開発』(共に日本経済新聞出版社)など、著書多数。
人手不足、人材不足、人材の多様化が同時進行するなかで、企業側にはどのような姿勢が望まれるのだろうか。守島教授が10年ほど前から提唱しているのが「全員戦力化」という考え方だ。
守島 「全員戦力化」は、文字どおり、「すべての人材を最有効活用していこう」というものです。これはごく当たり前の話で、多くの企業はこれまでも実践してきました。例えば、戦後の高度経済成長期に、日本企業は主に新卒の男性を正社員として一括採用し、年功序列、終身雇用といったメンバーシップ型の人事制度などで「全員戦力化」してきました。それが、1980年代には「ジャパン・アズ・ナンバーワン」といわれるほどの競争力をもたらしたのです。
しかし、バブル崩壊後、人件費を抑えるために、多くの企業は人材の選別を始めました。上位2~3割の優秀層に給与や研修機会を傾斜配分し、それ以外を“戦力外”扱いにしたのです。
もうひとつの大きな変化は、正規雇用と非正規雇用の区分が広がったことです。正規雇用は重要人材として手厚くフォローする一方、非正規雇用は現場を回すための低コスト人材として扱うようになりました。
経営環境の変化によって、こうした動きは致し方ない面もあったと思いますが、その後も多くの日本企業において、“新しい「全員戦力化」”を目指す動きが鈍かったように感じます。