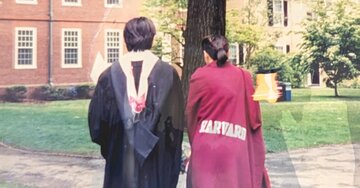ステップ3:伝える力(面接など、言語化しアウトプットする練習)
最後にアウトプットです。
自己分析はしっかりしている、業界・企業研究も十分、なのに面接で落ちてしまう……そんな学生が年々増えています。これは就職活動の最終ステップである「伝える力」、アウトプット力が足りないせいなのです。
伝える力とは、「何かを伝える」だけでなく、「どう伝えるか」「どんな姿勢で伝えるか」まで含めた総合力です。「優秀なのに面接で受からない」学生の典型的な3つのパターンを見ながら、対処方法を考えてみましょう。
■【パターン1】正解を求めすぎる学生
面接で落ちる学生に最も多い共通点は、「相手が求める答えを言おうとする」こと。「こう言うと評価される」「こう言った方が自分がよく見える」と計算をして、勝手に「いい子」になってしまうのです。
テストには正解がありますが、面接では自分が話していることが正解であるということを意識し、自信を持って話すことが重要です。今まで親の言う通りにしてきたり、大人の顔色を見て行動してきたりした人は、その延長線上で面接に臨むと、面接官には「活躍する可能性を感じない人」と映ってしまいます。
企業は「金太郎飴」のように同じ人、つまり個性の見えない学生を求めていません。大手企業が数千人単位の大規模なリストラを行う一方で、新卒に高額な初任給を提示するのは、「型にはまった人間」よりも「可能性を秘めた人材」が欲しいからです。そして、その可能性は個性からしか生まれません。
就職活動は「自分らしさ」と「企業らしさ」のマッチングの場です。他人の期待に合わせた「就職活動用の自分」ではなく、日々の経験からにじみ出る「本来の自分」を伝えることが何よりも大切です。
野球部に入っていたある学生は、グラウンドで大きな声で叫びながら、面接用の動画を撮影しました。その動画を見た瞬間、私の心はぐっと掴まれ、「これは通るな」と直感的に思いました。挑戦と個の力を重んじる気風で知られる大手商社の目に留まり、見事トップ内定していきました。
■【パターン2】器用だが熱意が伝わらない学生
器用な学生の多くは、これまで大きな挫折もなく、比較的スムーズに人生を歩んできた優等生です。正解を出すのは得意なのですが、自分の思いを相手に伝えるのは全く別のスキル。このため、面接では企業の印象に残りにくいのです。
こうした学生は「表面的にきれいにまとめる」のが上手です。しかし、そこに熱量や情熱が隠れてしまう。言うなれば「立派な包装の有名店の羊羹」なのです――見た目は端正で、中身も保証されているが、その中身には驚きがない。未知の部分や可能性を感じさせない人材に映ってしまうのです。
企業が重視しているのは、入社時点での「完成度」ではなく、その後の「成長曲線」です。
社会人スタート時点できれいにまとまっている人よりも、将来的に大きく化ける可能性を持つ人材の方が企業には魅力的です。そして、その可能性は、その人が持っているアツイ思い(熱意)、行動力といったものから判断されます。
行動力は、社会人訪問などの数を重ねることで示すことができます。ある学生は、教育実習やアルバイトをこなしながらも、社会人訪問を200人行い、見事日本の金融政策を担う中枢機関に内定していきました。
熱意やその思いをどう表現するか。結局、自己分析を究めて、ありのままの本音を自分の言葉を使って言語化し、さらにそれを人に伝える練習を何度も重ね慣れていくしかありません。つまり「伝える力」とは、表現の上手さではなく、どれだけ自分を理解し、本音で語れるかにかかっているのです。
■【パターン3】コミュニケーションが苦手な学生
コミュニケーションが苦手な学生の共通点は、端的にコミュニケーションを取ってこなかった人です。頭では色々考えられているのに、自分から発信したり、表現する場や機会がなかったりしたため、フォロワー的な立場にい続け、いざ面接となると言葉に詰まってしまいがちな傾向にあります。
とある吃音(きつおん)に悩んでいた学生の話です。頭の回転は早いのに、なかなか自分らしさを表現することができず、面接に苦手意識を持っていました。どんなことにも言えることとして、“練習量と成長幅は比例する”と考えています。彼も果敢に人前で話す練習を重ね、「どういう時に吃音が出るのか」を冷静に分析しました。この結果、「吃音が出た時はどうすればいいのか」の対処法を身につけることで、落ち着いて面接に臨めるようになったのです。実際に私と話している時も、ほぼ気付かないほどまでに彼は自分の話す力を磨き上げました。そして当然のことながら、彼の高い能力と努力できる胆力が評価され、多くの学生が憧れるコンサルティングファームのデータ分析という、自分の強みを発揮できる職種に内定していきました。
このように「苦手意識」は克服できるものです。避けるのはなく、向き合うことこそが「成長」につながるのです。