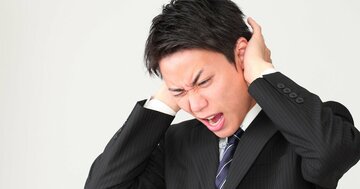「この本のおかげで出世できた」「チームのパフォーマンスが上がった」
そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4400社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「一生活躍し続けられる」メソッドや思考法を授ける本シリーズは、さまざまな業界から圧倒的な支持を集めている。今回は、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方を指南する。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
第3位:「急な方向転換」で現場が混乱
「よかれと思って、今週からこの方針でいこう」
そう言って管理職が急に方針を変える場面があります。
しかし、現場は混乱します。
計画していた準備が無駄になり、チームのエネルギーは失われます。
しかも、その方針変更が感覚や思いつきに基づくものであればなおさらです。
第2位:「肩代わり」で部下の成長を止める
「よかれと思って、代わりにやっておいたよ」
こうした「善意」も実は成長の機会を奪う行為です。
部下は責任を持って業務をやり遂げることで経験を積み、判断力を磨いていきます。
管理職が「自分でやった方が早い」と仕事を奪えば、組織は個人プレーに逆戻りし、誰も育ちません。
第1位:「感情寄り」でルールが崩れる
もっとも深刻なのは、「よかれと思って例外を認める」ことです。
たとえば、提出期限を守らなかった社員に対して「今回は事情もあるし…」と見逃す。
これが繰り返されると、職場にルールが機能しなくなり、秩序は崩壊します。
現場は「頑張った人が損をする」状態になり、士気が下がっていくのです。
仮面をかぶって、「よかれ」を疑う
リーダーの「よかれ」は、独善であることが多いのです。
組織に必要なのは、冷静で再現性のある判断です。
感情や思いつきで動くのではなく、仮面をかぶって、一貫性と仕組みを重視したマネジメントを徹底しましょう。
それが、現場を守るという本当の「善意」です。
(本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです)
株式会社識学 代表取締役社長
1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4400社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計170万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』(ダイヤモンド社)がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。