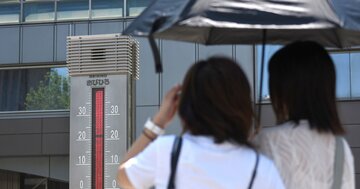線状降水帯をあまり伴わない豪雨とは?
近年の豪雨は、広範囲でより長期間降る「広域長期型」が特徴です。昔は狭い範囲に短時間にドカッと降っていたので、被害も地域限定型でした。近年は長く降り続き、且つ日本の広い範囲で降る雨が増えており、被害地域も広範囲に及んでいます。
線状降水帯の知名度が上がっていますが、これは狭い範囲に豪雨をもたらす現象です。最近の豪雨には、線状降水帯をあまり伴わない例も増えています。
2018年の西日本豪雨は線状降水帯が主因ではないという意味で象徴的な豪雨でした。長野県以西の数多くの観測点と北海道で、3日降水量(72時間降水量)での観測史上最大の降水を記録。関東と東北を除くほとんどの地域で観測史上最大の豪雨が3日間以上降り続いたのです。筒井康隆さんのパロディー小説『日本以外全部沈没』のように、「関東・東北以外全部沈没」を予期させるような豪雨でした。
実はこの豪雨は3日前に気象庁が緊急記者会見を開き、ほぼ完璧に予測ができていました。浸水域もハザードマップとほぼ一致。そこまで予測できていたにもかかわらず、被害は甚大だったのです。
西日本豪雨は、全国のニュース番組で緊急記者会見が何度も流れ、新聞でもとりあげられ、マスコミは全力で注意喚起を行っていました。それでも大きな被害になったのは、人々の関心の主軸がマスメディアから離れたからという見方もありますが、それは間違っているでしょう。なぜなら、気象系のネット界隈でも、この予測が大いに話題になり、注意喚起が強くなされたからです。
なぜ予測が完璧で、マスメディアでもネットメディアでも大いに話題となっていても、大災害が起こってしまったのでしょうか?
その理由は、無関心派及び危機感が稀薄な人が多数だったためだと考えています。これが、予測精度がどんなに向上しても、災害被害がほとんど減らない要因なのです。
気象現象に無関心な人や自分事としてとらえていない人が圧倒的多数であれば、残念ながらどんなに有用な情報を発信しても、無意味となってしまいます。
多くの人は関心を示しませんし、その情報を防災に活用することもありません。