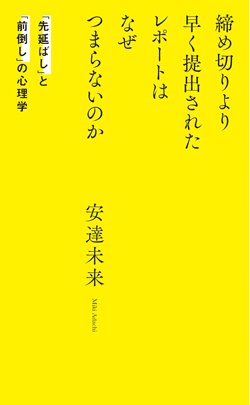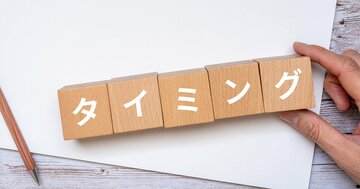この考え方は、先延ばしを回避するためのセルフコントロールを発揮できているともいえます。だからといって「セルフコントロールがきちんとできていますね」で終わる単純な話でもありません。
先延ばしをしないことをよしとする風潮は、現実社会に確実に存在しています。宿題の提出が早いと先生に褒められる、「仕事が早くて助かる!」と上司に評価してもらえる、などです。しかし、本当によいことばかりなのでしょうか。くり返しになりますが、早めに事を進めることには何の異論もありません。しかし、だからといってあまりにさっさと終わらせることが必ずしもよいとはいい切れないような気もします。
こうした見方については、先延ばしの研究ではほとんど扱われてきませんでした。「先延ばさないことにもメリット・デメリットがあるのではないか」「先延ばしの視点だけではなく、もっとタスクの進め方にシフトした見方が必要なのではないか」という問題意識に、私自身、先延ばしの研究を通して気付かされたのです。
学生は多くの授業を履修していて、それぞれにレポートや課題をかかえています。課題によって難易度やかかる時間も違いますし、好き嫌いや関心の程度も違います。それらにどのような順序でとりかかるかは、まさにタスクマネジメントに関わる問題といえるでしょう。
そして、これは学生のレポートに限らず、社会人にとっても身近なテーマです。働き方への意識や関心が高まる現代社会において、だれもが心身ともに健康な生活を送るためには、先延ばしの是正や改善だけでなく、効率的にタスクを進めていく方法を視野に入れる必要があります。