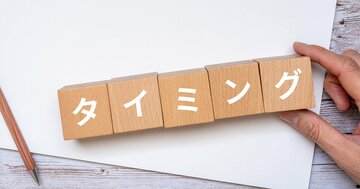この点こそ、私が長らく興味・関心を寄せてきたテーマであり、本記事で扱う「先延ばし」と「前倒し」の研究をはじめた経緯につながっていきます。学術の世界では、先延ばしの原因やメカニズムの解明、その対処に向けた提言に関する知見は数多く蓄積されてきました。しかし日常生活と照らし合わせて考えてみると、どこかで先延ばしの研究に対するモヤモヤした感覚が私のなかにありました。
先延ばしをしない人、もしくは的確な見通しや自信をもって積極的に先延ばしをする人は、学校の成績も悪くないし、精神的にも健康。それはなんとなく実感としてわかります。でも、それだけとは思えなかったのです。
私は、大学の授業で学生に課すレポートをすべてオンライン上で管理しています。レポートの内容、期限、オンライン上の提出場所を指示しておいて、そこに学生が提出する仕組みです。私の所属する大学で用いられている学習管理システムでは、その学生がいつ課題にとりかかったか、作業にどれくらいの時間をかけたか、最終的にいつ課題を提出したかなどがすべて記録され、確認できます。毎回、提出されるレポートをチェックしていくと、「提出日がやたらと早いな」と思うケースに出合うことがあります。
もちろん、期限を破って提出する先延ばし行為に比べると、高評価以外のなにものでもありませんし、早めの提出を労いたいとも思います。ただし、あまりに早い時期に提出されたレポートは、質がよくないことが多いのです。「さっさと終わらせた」感がヒシヒシと伝わってくる内容です。
仕事が早い=優秀
とは限らないワケ
「そんなレポートはダメ、受け取らない」と憤慨したり、「もっと時間をかけなさい」と注意したくなったりしているわけではありません。もちろん、どう見ても適当なレポートや、他人の文章をそのままコピーして貼り付けているコピペ(最近ではChatGPTとレポートに関する議論も話題になっていますね)レポートであれば、再提出を促すこともあります。ただし、私の関心はそこではなく、素朴に「なんでそんなに早く提出したいの?」というところにあります。学生からすると、「さっさと終わらせて遊びたいから」「めんどうなことこそ先に終わらせたい」などという言葉が返ってきそうです。