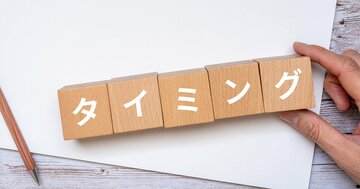イエール大学のシンらは、参加者の大学生に、起業のための提案書を作成してもらうという実験を行いました(注3)。提案書の作成中、画面にはその課題に関連しないYouTube動画のリンクが表示されていました。参加者は1本の動画が視聴できる低条件、4本の動画が視聴できる中条件、8本の動画が視聴できる高条件の3つの条件に分けられ、どのグループも動画を視聴できる状態で、提案書を作成しました。
その後、完成した提案書に対し、その提案内容がどれくらい創造的かを評価した結果、中条件、つまり4本の動画を視聴できる状態で作成された提案書の中身が、最も創造的であるという結果が得られたのです。このことから、先延ばしが少なかったり、過度に先延ばしたりするよりも、「適度な先延ばし」が予想外の発想や新たなアイディアの生産には効果的であることがわかりました。
確かに、仕事や課題が煮詰まったとき、締め切りが迫っていて先延ばしをしている場合ではなかったとしても、意図的にタスクを一旦中断することで、気分転換やリフレッシュができ、新たな考えを思いついたり、逆にはかどったりすることがあります。つまり、「先延ばしをする余裕はない!もう締め切りまで時間がないんだから!」というときでも、一時的に後回しにしてみることは、タスクマネジメントの1つといえます。
気分転換がタスクの完了に向けてよい効果を生むかもしれませんし、思いがけずに有益な情報を得たり、タスクの完了に向けてのよい準備・計画段階になったりすることもあります。一時的な先延ばしがよりよい成果をもたらすこともあるのです。
「先延ばし」を責める前に
「前倒し」の落とし穴を見よ
このように考えていくと、そもそも先延ばしという考え方自体を見直す必要があるように思います。実際に、あるタスクを先延ばしている間は、そのトレードオフとして別のタスクには早めにとりかかっていることもあるわけです。重要なのは、どうやって効率的にタスクをマネジメントすればよいのかを考えることです。