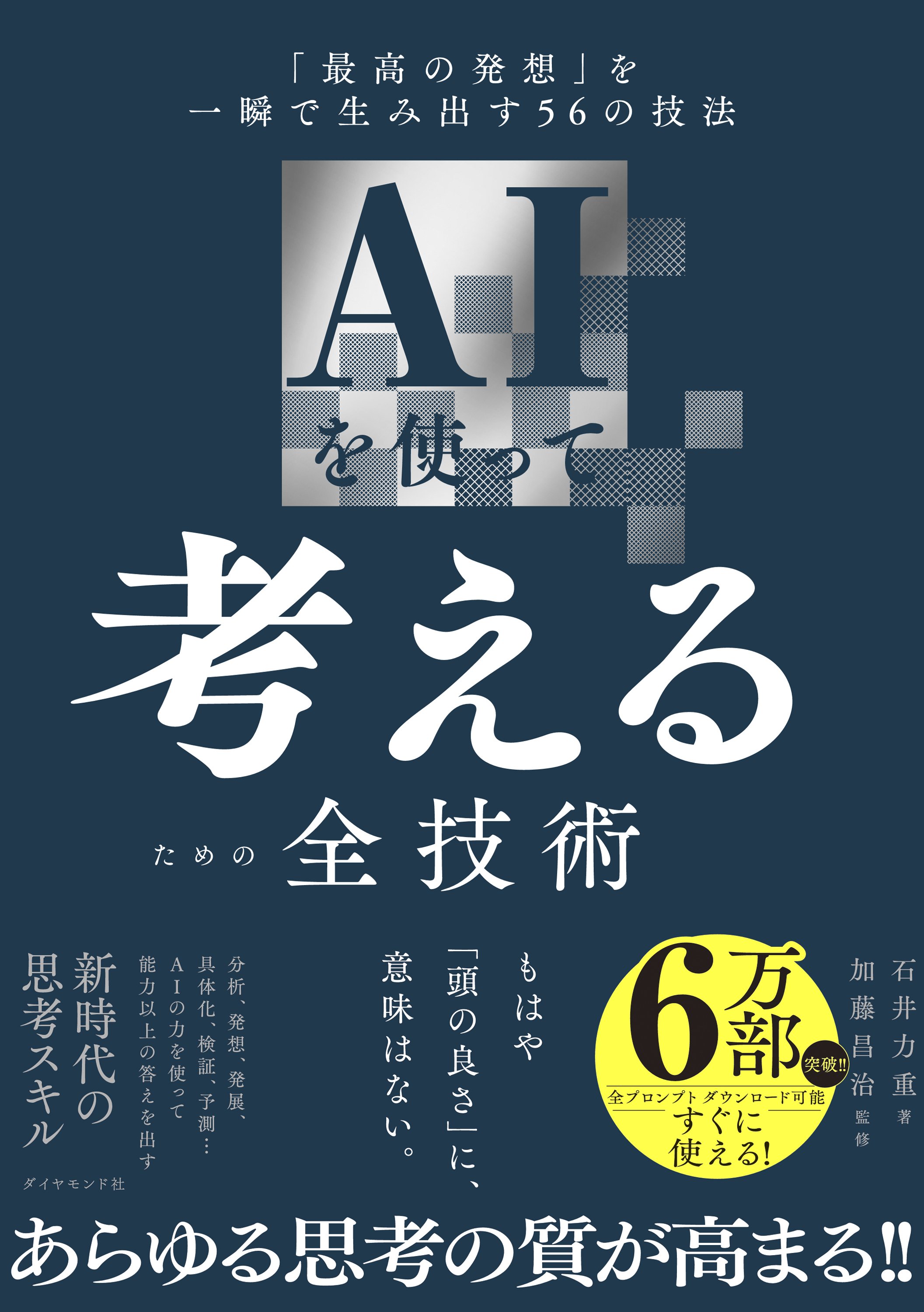以下は、異なる形式で提出されたアイデアリストを統一されたシンプルなリストに変換し、通し番号を付けたものです。元の表現をできるだけ変更せずに保持し、誤字や脱字がある場合は【】内に訂正案を記載しています。
1. 研修をゲーム化する。参加者に目標を設定させ、達成度に応じて点数やバッジを付与する。競争心をくすぐり、楽しみながら学習できるよう工夫する。
2. 参加者のニーズに合わせたカスタマイズ可能な研修コースを用意する。個人の関心や経験に応じて、カリキュラムをパーソナライズできるよう設計する。
3. 実践的な演習に重点を置く。座学ではなく、ワークショップや体験型の【円周】を多く取り入れ、実践を通して学ぶ機会を増やす【訂正案: セッション】。
4. 有名講師や著名人を招聘する。参加者の憧れの人物を講師に迎え、モチベーションを高める。講師の人気で関心を集められるよう工夫する。
5. 研修の成果を「見える化」する。作品や成果物を発表する場を設け、達成感を味わえるようにする。同僚からの評価も得られ、やりがいにつながる。
6. 研修の場所を変える。普段とは違う環境に身を置き、新鮮な気持ちで学べるよう配慮する。レンタルスペースやリゾート地での開催など、斬新な会場を検討する。
7. 研修の内容に娯楽的な要素を加える。趣味や娯楽を学びに取り入れ、楽しみながら知識やスキルを身につけられるよう工夫する。
8. 参加者同士の交流を深められる機会を設ける。グループワークやレクリエーションを通して、参加者同士の親睦を深め、研修への意欲を高められるよう配慮する。
9. 研修の成果に応じた報酬を用意する。優秀な成績を収めた参加者に対し、ボーナスや昇進などのインセンティブを設ける。目標達成への動機づけとなる。
10. 研修を複数回に分けて実施する。一気に知識を詰め込むのではなく、複数回に分けて、少しずつ学習していけるよう設計する。集中力の維持と理解の定着を図る。
11. 研修のテーマに関連するゲームやクイズを用意し、参加者同士で競争させる。勝者には賞品やポイントを与える。楽しみながら学習できる研修にする。
12. 研修の内容を動画や漫画などのビジュアルなメディアで表現し、参加者に見せる。視覚的に印象に残る研修にする。
13. 研修の前に参加者に事前課題を出し、研修の中で発表やディスカッションを行う。参加者の関心や意見を引き出す研修にする。
14. 研修の後に参加者にフィードバックや感想を書かせ、研修の効果や改善点を評価する。参加者の声を反映させる研修にする。
15. 研修のテーマに関連する実際の事例や問題を紹介し、参加者に解決策を考えさせる。実践的なスキルや知識を身につける研修にする。
16. 現場の課題解決型研修: チームで実際の案件に取り組み、課題解決に向けて議論し、解決策を導き出す研修。翌日から実践で活かせるスキルを習得し、仕事へのモチベーションを高める。
17. アクティブラーニング研修: ロールプレイングやシミュレーション、ゲームやクイズなど、参加者が主体的に活動する研修。楽しみながら実践的なスキルを習得し、学習効果を高める。
18. スキルアップ研修: 専門家による講義や演習を通して、専門知識やスキルを深める研修。最新技術やトレンドを学び、自身のスキルアップに繋げる。
19. 異業種交流研修: 異なる業界の企業との交流を通して、新しい視点やアイデアを獲得し、人脈を広げる研修。自社の課題解決に繋がるヒントを得られる。
20. 著名人・専門家による講演: 第一線で活躍する著名人や専門家から、生の声を聞き、モチベーションを高め、仕事への意欲を向上させる研修。質疑応答の時間を設け、疑問を解消できる。
21. キャリアビジョン研修: 自己分析やキャリアプランニングを通して、自身のキャリアビジョンを明確化する研修。目標達成に向けて具体的な行動計画を立てられる。
22. チームビルディング研修: チームワークを高めるアクティビティやワークショップを通して、コミュニケーション能力や協調性を育む研修。チーム目標達成に向けた共通認識を醸成する。
23. エンターテイメント研修: ストーリー性のある内容やゲームを取り入れ、楽しみながら学べる研修。参加者の集中力を維持し、競争心を刺激する。
24. ゲーミフィケーションを取り入れ、達成ごとにバッジやポイントを授与する。
25. 研修終了後に参加者同士のネットワーキングイベントを開催する。
26. 実践的なプロジェクトを組み込み、チームでの成果物作成を目指す。
27. VRやAR技術を用いて、仮想環境での体験学習を提供する。
28. 専門家や業界のリーダーを招待し、インスピレーションを与えるセッションを設ける。
29. 参加者が自分の学びたいテーマを選択できるカスタマイズ可能なコースを用意する。
30. 研修前の事前課題で参加者の関心を引き、学習意欲を刺激する。
31. ピアレビューを取り入れ、参加者間でフィードバックを交換する。
32. ミニコンペティションを開催し、優勝者には特別な報酬を提供する。
33. 参加者が研修内容を社内外にシェアするためのプレゼンテーションスキル講座を組み込む。
わずかな時間で、33案をスパッとリスト化してくれました。わざと残した「円周」の誤字はAIで指摘され、「セッション」と訂正案が付されていました。とはいえ「人材」と「人財」のように、こだわりがあって書いている可能性もあるので、どう表記するかは最終的に人間が判断しましょう。
さて、きれいなリストができたところで、技法「チームの創造力」の第2段階。先のスレッドに続けて、次の内容でAIに指示します。
これらのアイデアを確認し、類似したものをグループ化してください。ただし、過度に集約せず、アイデアの多様性を保持することが重要です。似たアイデアを1つにまとめる際は、集約されたアイデアごとに、関連するオリジナルのアイデアを括弧内に含めてください。また、アイデアの核心を捉え、可能なかぎり具体的かつ明確な形で集約したアイデアを提示してください。
1つのスレッドで継続できるのは本当にありがたいですね。
以下に、類似したアイデアをグループ化し、多様性を保ちつつも、核心を捉えた形で集約したアイデアを提示します。関連するオリジナルのアイデア番号を括弧内に含めます。
1.ゲーミフィケーションと競争を取り入れた研修:研修をゲーム化し、参加者間の競争を促進することで、学習のモチベーションを高める。達成度に応じてポイントやバッジを授与し、勝者には賞品を提供する。(1, 11, 24)
2.カスタマイズ可能な学習コースの提供:参加者のニーズや関心に合わせて、パーソナライズされた研修コースを設計。参加者が自ら学びたいテーマを選択できるようにする。(2, 29)
3.実践的な演習とプロジェクトに焦点を当てた研修:実践を通じて学ぶ機会を増やすために、ワークショップや体験型セッション、実際のプロジェクト作成を組み込む。(3, 15, 26)
4.専門家や著名人を招聘したインスピレーションセッション:講師として著名人や業界のリーダーを迎え、参加者のモチベーションと仕事への意欲を高める。(4, 20, 28)
5.研修成果の「見える化」と報酬の提供:成果物の発表や評価を通じて達成感を味わわせ、優秀な成績を収めた参加者には報酬やインセンティブを提供する。(5, 9, 32)
6.新鮮な学習環境の提供:普段と異なる場所での研修を通じて、新鮮な気持ちで学習できるよう配慮する。(6)
7.娯楽と学習の融合:趣味や娯楽的要素を取り入れた学習アクティビティを通じて、楽しみながら知識やスキルを身につける。(7, 23)
8.参加者同士の交流とチームビルディング:グループワークやレクリエーションを通して参加者間の親睦を深め、チームワークを高める。(8, 22)
9.分割して実施する研修プログラム:知識を少しずつ学習していけるよう、研修を複数回に分けて実施する。(10)
10.ビジュアルメディアを活用した学習:動画や漫画などのビジュアルなメディアを用いて、視覚的に印象に残る学習体験を提供する。(12)
11.事前課題とフィードバックを取り入れた学習:研修前の事前課題で学習意欲を刺激し、研修後には参加者からのフィードバックや感想を集める。(13, 14, 30)
12.アクティブラーニングとキャリアビジョンの明確化:ロールプレイングやシミュレーションを含むアクティブラーニングと、自己分析やキャリアプランニングを通じてキャリアビジョンを明確化する研修。(17, 21)
13.異業種交流とネットワーキング:異業種の企業との交流や研修終了後のネットワーキングイベントを通じて、新しい視点や人脈を広げる。(19, 25)
14.テクノロジーを活用した体験学習:VRやAR技術を用いた仮想環境での体験学習を提供し、参加者の集中力を維持する。(27)
15.ピアレビューとプレゼンテーションスキルの強化:参加者間でのフィードバック交換と、研修内容を社内外にシェアするためのプレゼンテーションスキル講座を含む。(31, 33)
これらの集約は、アイデアの多様性を保持しつつ、似たアイデアを効果的にグループ化しています。
33個あったアイデアが15個に。類似したアイデアをかなりスッキリとまとめてくれて、かつ具体的な表記に変更してくれました。なお、この段階で「珠玉のアイデアだと思っていた案が、他の案に吸収されてしまった」と感じたならば、リストの末尾にその案を復活(追加)させてもいいでしょう。
さて、集約した15個のアイデア、なかなかじゃないですか? もともとのアイデア群は方向性が偏っていたり内容が薄かったりしましたが、全部を重ね合わせて統合、整理をすると、経験豊かなアイデアパーソンが考え出したかのようなレベルの高いアイデア群になっています。結果として、属人性も消えていますね。
このリストをベースに、チームメンバーでブレインストーミングを行ってさらにアイデアを考えるのもよいですし、AIに発展案や具体案を考えてもらうのもいいでしょう。アイデアを募ってみたものの、その処理に困っていた。そんなリーダーにもぜひ使ってほしい技法です。
チームの人数が多く、各案を比較・検討するのに時間がかかりそう。いくつか似ている案があるけれど統合する方法が見えにくい。「誰のアイデアか」に囚われずフラットに議論を進めたい。そんなときにおすすめの技法です。
技法その21「チームの創造力」、ぜひ活用してみてください。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、分析、発想、発展、具体化、検証、予測といった“頭を使う作業”にAIを活用する方法を多数紹介しています)