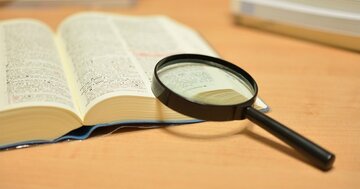2019年の内閣府の発表では、40~64歳のひきこもりシニアは約61万3000人にのぼるとされるが、彼らの多くには、親亡き後の生活を支援する家族がいない。
子どもがいる親の側も、安心してはいられない。2000年以降、長生きする人が急増し、要介護期間や死亡時に子どもがいても、その子どももかなりの高齢であることが容易に想定できる。
「老いては子に従え」と、子どもがいるから老後は安心であるという時代では、もはやなくなっているのだ。
頼れる家族がいないと
病院も介護施設も門前払いに
以上のように、結婚しようがしまいが、子どもがいようがいまいが、長生きをすれば、最後はおひとりさまになる可能性は誰にでも起こり得る。これまでの日本では、自立できなくなった時には家族が支援したり、面倒をみたりするのが当たり前だとされてきた。
ところが、おひとりさまの増加で、いざというときに支援してくれる家族がいない、あるいは家族はいるが、頼れないというケースが珍しくなくなっている。
老、病、死に直面すると、誰しもが誰かの支援を受けざるを得なくなる。例えば入院や入所時に身元保証人を求める病院や介護施設はたくさんある。
2018年に厚生労働省は、身元保証人がいないことを理由に、病院は患者の入院を拒否してはならないという通知を都道府県に出している。
しかし神奈川県病院協会や第2東京弁護士会などが実施した各種調査によれば、9割以上の医療機関や介護施設で身元保証人を求めており、親族や民間事業者による保証人がいない場合には、入院や入所を拒否するケースが報告されている。
保証人になる親族がいない人に判断能力がなくなった場合、成年後見人をつけたとしても、後見人は医療契約を代理することはできるが、介護支援内容や医療行為への同意は認められていないので、手術や延命措置について本人に代わって判断してくれる人がいないことが、施設側が受け入れをためらう背景にある。