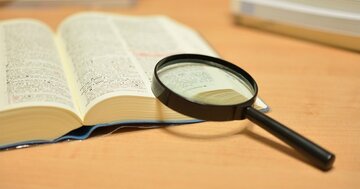自立できなくなる前に
やるべきことは数多い
施設入所時には身元保証人がいても、保証人が先に亡くなり、保証人がいなくなるケースもある。
保証人がいない人の経費不払いを心配する声も現場では大きくなっている。本人に支払い能力があったとしても、死亡した場合に回収できない可能性があるからだ。
しかし生活保護受給者なら、入院費や介護費は全額給付され、自己負担はない。保証人がいない場合と比べると、病院や施設側からすれば、生活保護受給者の方が不払いの心配はないのだ。
こうした身寄りなし問題は、自立して生活している時には顕在化しない。そのため、希望する医療や介護サービス、延命措置の可否、緊急連絡先や希望する納骨方法など、元気なうちに、自分の意思を書き記している人は多いとはいえないのが現状だ。
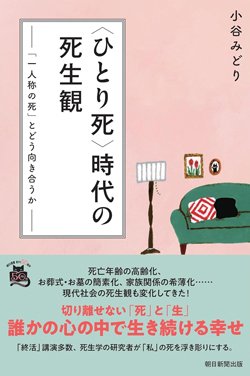 『〈ひとり死〉時代の死生観「一人称の死」とどう向き合うか』(小谷みどり、朝日新聞出版)
『〈ひとり死〉時代の死生観「一人称の死」とどう向き合うか』(小谷みどり、朝日新聞出版)
神奈川県横須賀市では2018年、あらかじめ登録した市民の終活情報を、いざというときに本人に代わって、病院、消防、福祉事務所などに開示するサービスを全国に先駆けて開始した。現在、大和市、逗子市、鎌倉市などのほか、豊島区が東京都23区で初めて登録制度をスタートさせているし、横浜市でも制度の導入が決まっている。
自立できなくなった時の備えとして、自分の意思とそれを伝えてくれる代理人の存在は必要不可欠なのだ。
日本では、人が高齢になり自立できなくなってから、なかでも人が亡くなって以降のことは、家族や子孫が担うべきとされてきた。
しかし血縁、親族ネットワークだけでは老い、病、死を永続的に支え続けることは不可能なところまで、日本の社会は変容している。
自立できなくなった後に頼れる家族がいることがもはや当たり前の社会ではなくなっている。