取材で印象深かったのは、担当者の「交通の世界では『出し抜き屋』では絶対うまくいかない。みんなやっているからこの指とまれの『つながり屋』でなければならない」との言葉だった。
2021年3月の「totra」を皮切りに、2021年に2種、2022年に9種、2023年に2種、2024年に1種、そして、今年3月に15番目となる「KURURU」がサービスを開始しており、今後も拡大を予定している。
また、長野県のバス事業者「のざわ温泉交通」は昨年12月、自社でカードは発行せずに地域サーバーにのみ接続して10カードに対応した。温泉・スキーで訪れる首都圏の観光客は10カードを持っているとの判断だった。資本金1000万円の小規模事業者でも導入できたということは、片利用の理想像が形を変えて実現したと言えるだろう。
 JR東日本プレスリリースより 拡大画像表示
JR東日本プレスリリースより 拡大画像表示
地域連携ICカードは将来的にスマホアプリへと進化する。冒頭に記した「Suica Renaissance」には、モバイルSuicaを発展させたSuicaアプリをベースに、マイナンバーカードと連携したサービスが利用できる「ご当地 Suica(仮称)」の導入を掲げている。
JR東日本はセンターサーバー式のSuicaを「共通プラットフォーム」として構築し、他事業者のニーズに応じて提供するとしており、将来的には海外マーケットへの拡大を目指すという。地域連携ICカードの拡大は壮大な構想の成否を占う第一歩、といっても過言ではないだろう。
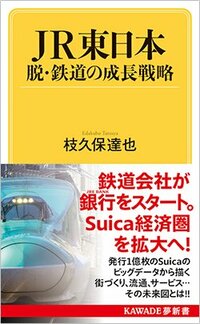 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。







