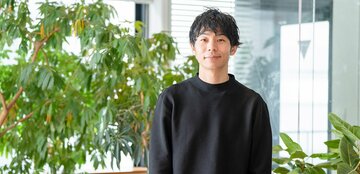二項対立を改善する
テクノロジーPol.is
――アメリカの民主党と共和党の分断も激しいですが、両党それぞれの中でも分裂が起きていると聞きます。日本でも欧州でも分断は激しいですね。そうした二項対立問題をテクノロジーで緩和できることも、本書の核心の一つでしょうか。前述の安野さんたちのブロードリスニングの他にも、台湾でのデジタル民主主義の実践例で活用されているテクノロジー「Pol.is」についても本書では詳述されています。
Pol.isは、合意形成のプロセスを可視化するソーシャルメディア・ツールです。例えば、ある事案に対して住民の意見をシステムで集めた上で、具体的な質問を1つして、住民に賛成・反対・パス(不確定)の3択で意思表示してもらいます。すると、A Iがリアルタイムで「オピニオン・マップ」を作り、意見が近い者のグループ分けと、その中での各住民の位置付けを表示します。
そのマップによって、グループ間の意見の相違や歩み寄りの余地を理解できるようになっています。追加の質問をすることで意見分布の詳細が明らかになると、どのグループでも同意が得られそうな意見をつくることができるのです。
複数の意見グループから賛成される意見を、みんなで考えていくことで、グループ間を結びつけ、二項対立ではない熟議が促されていきます。
――本書では、SNSでの「エコーチェンバー」の負の側面を解説した後、Pol.isの良さを詳述されています。意見対立を煽るようになってしまっているSNSを「脱構築」すると表現されています。
脱構築は、フランスの哲学者ジャック・デリダが発した難しい概念ですが、私は「意見の二項対立をずらす」という意味合いで提示しました。
SNSの中での対立はいろいろあります。藤田直哉さん(編注:文芸評論家、日本映画大学准教授)が挙げられている例を出すと、フェミニズムの考え方について、しばしば男性と女性の間で激論が交わされます。しかし、意見を対立させている個々の当事者は、男性あるいは女性以外にも多くの属性を備えています。
例えば、フェミニズム論で口論している男性と女性が共に労働条件の悪い企業に勤務しているとしたら、待遇の改善策という面では繋がることができるでしょう。その連帯感をきっかけにフェミニズム論でも折り合いのための話し合いが始まる、ということはあり得ます。
ある人は、男性であり、劣悪条件の企業に勤務するビジネスパーソンであり、オリックス・バファローズのファンであり、と実にいろいろなグループに属している。そのことに気づくと、多様な人々と繋がったり、折り合ったりできます。今日のテクノロジーはそれを促進できるのですが、まだまだ生かせていません。とはいえ、Pol.isのようなテクノロジーの活用は、世界各地でどんどん広がっています。
――いろいろな属性が一人の人の中に重なり合っていることを、本書では「交差的アイデンティティ」の概念で論じています。プルラリティの鍵となる考え方ですね。
タンさんは、「グッド・イナフ」ということもしばしば提言されています。意見対立が起きている時に、無理に意見統一するのではなく、「今はこれぐらいにしておきましょう」という具合に治める方法です。時間を置けば、新たな道が開けてくるかもしれないし、前述したように他の関係性から折り合いを探ろうとするかもしれません。「課題解決は、次の世代に委ねましょう」と長期スタンスになることもあるでしょう。
この方法は昔からあったと思うのですが、タンさんの提言の今日的な意味合いは、テクノロジーの存在があることです。前述した通り、テクノロジーは、効率的に、即時に、最適化に向かう、という特性があります。その危うさへの批判の文脈で、警鐘を鳴らしている面もあります。
――そもそも、本書『テクノ専制とコモンへの道』やオードリー・タン、グレン・ワイル著『PLURALITY』で論じているプルラリティ(多元性)は、ダイバーシティ(多様性)とどう違いますか。
多様性は「状態」です。多様性を実現しようなどと言わなくて、人間社会は最初から多様な状態にあります。人それぞれ、考え方も価値観も違います。でも、前述したように、多様である中で生きるのは本来、難しい。
同時に、多様であるからこそ人と人との摩擦の中で新しいものが生まれ、イノベーションが起き、社会が豊かになっていく。
多元性とは、そういう多様性が何か新しいものを生み出したり、世界全体を豊かにしていくことです。そして、その変化を支援するテクノロジーもプルラリティと呼んでいます。多様性は「静的」(スタティック)なもので、多元性は「動的」(ダイナミック)なものです。
*中編は、「ジョン・デューイ、柄谷行人、ダロン・アセモグルなど、プルラリティに影響を与えた思想家について」で、明日公開予定です。
1990年、神戸市生まれ。法政大学社会学部准教授。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。日本学術振興会特別研究員、コロンビア大学客員研究員などを経て現職。著作に『ベルナール・スティグレールの哲学 人新世の技術論』(法政大学出版局)、『テクノ専制とコモンへの道』(集英社新書)。