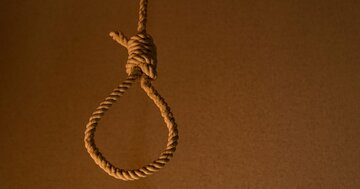戦後最高に無期刑受刑者が多かったのは2013年で1843人でした。その後、緩やかに減少し、2022年には1688人まで減少しています。では、この1700人ほどの無期刑受刑者がいる中で、仮釈放はどのように運用がなされているのでしょうか。
この10年で新たに無期刑受刑者で仮釈放が認められた人の平均年数は2013年の31年2ヵ月から2020年の37年6ヵ月の間を行ったり来たりする値で推移しています。一方で2022年の新規に仮釈放が許可された無期刑受刑者の平均在所期間は45年3ヵ月でした。つまり、「10年や20年で仮釈放される」という運用実態にはなっていないことが分かります。数字を決められる有期刑は最大で、「(ふたつ以上の罪を犯したときに)30年」です。そのことからも、無期刑の仮釈放までの収容期間が30年より下回る形で運用されることは想像し難いでしょう。
また、前ページの表からも分かるように、新規で仮釈放になった人の数は2019年を除いていずれも1桁の数字となっています。最新の2022年に至っては1688人中の5名が新規に仮釈放となっただけであって、その平均在所期間も45年を超えています。
受刑者の高齢化が進み
出る前に亡くなるケースも
確かに10年や20年のようなスパンで仮釈放にはなっていないとしても、「いずれ出てくる」という部分には変わりがないので、やはり死刑廃止には「終身刑が必要であろう」という意見が出てくるかもしれません。しかし、表の右端にある「死亡した無期刑受刑者」の数を見てみてください。新規で仮釈放となった受刑者の数は1桁台の数字であったのに対して、少ない年で14名が、多い年で41名が刑事施設の中で亡くなっていることが分かります。
つまり、日本の無期刑は現在約1700人ほどが収容され、先ほど確認した厳しい基準をクリアした5人から10人ほどの受刑者が仮釈放を認められ、その2倍から4倍の人たちは仮釈放が認められることなく亡くなっていることが分かります。このように、仮釈放が認められる要件を満たしたごく僅かな人だけが仮釈放されるだけであって、日本の無期刑は実質的に終身刑としての運用がなされているのです。